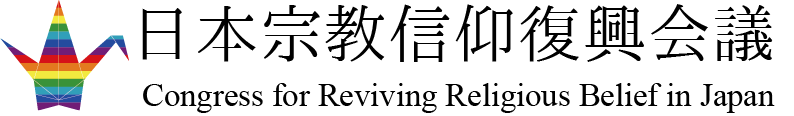信仰と科学の関係比較(水谷 周)
信仰と科学の関係について多くの議論を経てきた。昨今は脳科学の発達により宗教現象もかなり説明される面が出てきたようだ。また人工知能AIが人間を越えそうだという新たな話題もある。ここでは三大宗教における両者の関係を比較してみたい。
ア.キリスト教と近代科学の発達
古くギリシアにおいては、プラトンらの概念的なイデアの世界が提示されたことは周知である。現象世界の外にもう一つの世界を想定する発想であった。こうした思索は、理性(ロゴス)の働きとされた。このようなもう一つの世界を想定することは、中世のキリスト教においても行われた。それは神の啓示が主軸となりつつも、その理解のためとして、人に理性(ラチオ)を認めたのであった。
ところが近代にいたるや、人の理性(リーズン)は独り歩きを始めたのである。それがデカルトの「我思う、故に我在り」という言葉に集約されている。中世の神学が人間中心となることで、神の諸側面を剥ぎ落されて哲学が生み出され、神の啓示による法ではなく、理性による科学が産声を上げることとなった。この推移は徐々に進んだのであって、当初から科学者は神と対決することを目指したのではなかった。かれらは自然という現象の中に法則を見出すことを目指すことによって、そこに神以外の法則世界を見出し、それを樹立していったのであった。
その間、科学者たちはあくまで現象とは自らは別物として、客体化していたのである。以上のような、現象自体に法則を見出すことを眼目とし、他方その法則は自分自身とは切り離して捉えるという基本姿勢は、今日現在も全く変わっていない、それは科学のいわゆる客観性を担保するための大前提となっている。
イ.仏教の場合
仏教の場合を見てみよう。仏教においても現象世界に自然の法則を見出す点は、西欧の科学と軌を一にしている。それがいわゆる、生々流転であり輪廻転生の法といわれ、それは諸行無常という表現にもつながっている。初めもなければ終わりもなく、あるのは諸物の縁起という因果関係だけと理解するのである。
西欧の科学と異なるのは、科学では人間は現象とは別物で、客観視されるのであるが仏教ではそうではなく、自分は自然現象の一部でありその中に没している姿を描くのである。それが無我ということになる。仏教で悟りを開くとは、小さい自分である小私を脱して、大きな自分、大私になることだとも言われるが、この表現は分かりやすいかと思われる。しかし「分かりやすい」とはいっても、本当に悟りを開くことなどは容易でないことは言うまでもない。
ウ.イスラームの場合
以上と対比して、イスラームの立場は、西欧世界に近いとも言える。つまり、自然の現象自体の法則的世界を見出すことに躊躇はない。その姿勢が中世における、イスラーム科学の大きな原動力となったことは間違いない。天文学、医学、数学、化学など、多数のムスリム科学者が輩出した。多くはラテン語に翻訳されて、西欧世界にもたらされた。天動説はコペルニクスが発案したかのように言われてきたが、最近の研究ではそうでもないということだ。それはラテン語に訳されたアラブ文献にあったのを、借用していたということで、昨今はコペルニクスの評価は低下している。
それほどであったイスラーム科学であったが、そこでも人間観としては自然現象とは独立独歩で客体化されて見られていたことは、西欧の科学と同じであった。
ただしイスラームが西欧の立場と基本的に異なったのは、次の点であった。つまりイスラームでは、すべては絶対主のアッラーの創造と支配の下にあるということが、徹頭徹尾堅持されてきたという点である。だからアッラーから離れ、ましてや対立することなど、おそれ多くも頭には浮かばないのであった。イスラームでは創造主の存在があくまで大前提である。他方西欧の科学は、神の存在との対決姿勢が顕著で、二律背反という構造になってしまった。
エ.残る疑問点
イスラームの絶対主の支配は一貫して維持されてきた。ところが西欧の科学の発達は、神支配の拒否へと向かったのであったが、この違いはどこから来たのかということである。短絡的な回答は存在しない。
キリスト教諸国における宗教支配は、それを拒否した王権の発達により、両者が対立する羽目となった。ということは、それほどに宗教支配がいずれ排斥されねばならないほどに、人々の生活を脅かすものになって来ていたということになる。他方、イスラーム諸国における支配権力は、そこまでの拒否反応は引き起こさなかった。つまりそれなりに、民衆の支持を得ており、さまざまな不満などはあったに違いないにしても、何とかそれが広範な反旗を翻すには至らなかったのであった。
これはもちろん結果論であるが、イスラームの支配領域は広大で多民族であったが、中東の強みである東西貿易を主軸とした社会的紐帯はゆるぎなく、また政教一致の観念はキリスト教社会よりも根強いので、教義に基づく慈悲や正義といった諸価値の社会的浸透度が高かったと、仮説として推察することも可能である。
要するに、基本的で総合的な疑問点は、初めから明確な答えなどないのである。何とかわれわれはより良い理解を持とうとしているだけであり、これ以上この方向での詮索は控えることとしても、叱責を浴びることもないだろう。
<終わり>
イスラームの正義(水谷 周)
多数の活動家は、自らが正義を求めて行動していると自覚していると見られるので、「正義」概念が注目されることとなる。つまり背景として、「正義」や「不正」の感覚は、日本の社会以上に鋭く日常生活に浸透しているということがある。日本語で正義というと、どこか日常用語でない感覚があることからも判明するだろう(水谷周『イスラーム信仰概論』明石書店、2016年。106~109頁参照。)。
定義としては、アッラーに認められた人間の正当な権利(ハック)が実現しているかどうかということであるが、権利と真理は同一の用語であり、正義(アドゥル)とは真理を愛することでもあるとされる。
権利は平等でも能力や生産量の実質が不平等であれば、最後の審判における報奨はどうなるのか。そのような場合、悪平等ではない実質上の平等が与えられるとされる。
正義と慈悲の関係も議論される。正義の権利を持つ人がそれを譲渡あるいは放棄して慈悲を優先させる場合には、それは是認される。例えば、盗もうとした人を、慈悲でもってそれを許すようなケースである。
クルアーンには次の通り、正義(アドゥル)という名詞形では、14回出てくる。
「本当にアッラーは、公正と善行、そして近親に対する贈与を命じ、またすべての醜い行いと邪悪、そして違反を禁じられる。」(蜜蜂章16:90)
「無法者がアッラーの命令に立ち返るまで戦いなさい。だがかれらが立ち返ったならば、正義(アドゥル)と公平(キスト)を旨としてかれらの間を調停しなさい。」(部屋章49:9)
「実にわれは明証を授けて使徒たちを遣わし、またかれらと一緒に、啓典と(正邪の)秤を下した。それは人々が正義(キスト)を行うためである。」(鉄章57:25)
ところでイスラームの正義の概念は、喧嘩両成敗といった日本になじみのある発想ではない。物事の内実に入って実質的に相対立している二者間の衡平を図る、つまりそれで本来両者が保持すべき正当な権利が確保されているかどうかという問題である。
そうすると当事者のそれぞれが保持するという権利が重要な要因となる。しかしその権利は例えば相続権などは比較的細かにクルアーンでも明記されているが、全般的には詳細な規定はない。そこはイスラーム法学の発達を待たなければならなかった。
ところが大きな事案、例えばパレスチナ問題などになると、事態はそれほどには単純ではない。何をもって認められた権利と考えるのか?合意された基準は、必ずしも存在していない。だからそれぞれの抵抗運動で自分が正しいと考える権利を持ち出す事態を招くこととなる。そのいずれもが、アッラーに認められていると信じてのことである。遺憾ながら、古典であれ、現代版であれ、神学書や道徳書にはそのような具体的な事例に即した検討は示されておらず、いろいろの解釈を呼び込む結果となる。
神学的に定かにされず、結局論拠としてはより明確な法学に求めることとなり、それが侵略者に対する神命による戦いである聖戦のジハード論ということになるのである。
現世の諸問題から神学世界に飛躍する習癖を是正する必要がある。そのためには何をどうすればいいのか。過去への猛省を基礎に、事態の改善の努力は続けられている。例えば、旧来の漠然とした正義概念に留まらず、同時に他者の権利も互いに認めあう形での理論構築の試みである。他方、こういった努力は、現実世界における世界的な政治経済上の公正さの実現と手を取り合う必要も当然ある。だがムスリムなら、そのような壮大な課題の実現には、やはりアッラーの御助力をお願いしようというのかも知れない。
イ.不正
不正(ズゥルム)は一般的には、他者の権利を不当に奪うことであるとされる。アッラーは人間の服従を求める権利があるが、信仰しない者はその権利を犯していることになり、したがってアッラーに対して不正を犯していることとなる。
「本当にアッラーは決して人間を害されない。だが人間は自らを害する。」(ユーヌス章10:44)
クルアーンの規定上、政治的な不正の詳論は見られずに、利子、詐欺、強奪、賭け事、盗み、賄賂など経済的なものだけが列挙される。政治面での詳論もあれば、相当な政治的なガス抜きになっていたのかも知れない。例えば、次のような調子である。
「あなたがた信仰する者よ、(真の)信者ならばアッラーを畏れ、利息の残額を帳消しにしなさい。・・・だがあなたがたが悔い改めるならば、あなたがたの元金は収得できる。(人々を)不当に扱わなければ、あなたがたも不当に扱われない。」(雌牛章2:278、279)
ウ.最後に
信仰は思想や信念の体系として、さまざまな人の要望や願いを吸収する力がある。それが共同体にとって穏当で建設的な形で行われるように、常に注視し、過激に走り脱線しないようにするのは、やはり信仰の一端であるということになるのだろう。
日常の祈りーその2(水谷 周)
前回の「その1」に続き、第2回目です。今度は、中国は雲南省という片田舎で活動していたイギリス人宣教師とインドで活躍して世界的に知られたマザー・テレサの言行録から紹介することにします。
このイギリス人はほとんど知られていない事例です。他方、マザー・テレサは極端に知られているケースです。こと「祈り」の意義という視点からは、有名かどうかは、全く関係ない話です。それも合わせて、よく心することにしましょう。
これは日常的に限界の生活を強いられているような現場です。つまり平時と有事が合体したようなケースです。そのようなケースとして挙げられるのは、『信仰による祈り(注1)』の著者の場合でしょう。著者フレイザーは20世紀初頭、英国より派遣された宣教師ですが、行き先は中国の雲南省にある3000米の山奥でした。もちろん生活はミニマムなレベルで、人々は彼の話に耳を傾ける余裕などは全くなかったのでした。そこでフレイザーは足掛け10年間、布教活動としては辛酸をなめる日々を送ることになりました。そして、10年経過を目途として、失望の内に帰国を決心しました。以下は、この間の言行録です。
ここに私たちの働きを実らせる神の方法が見えるー祈り、信仰、忍耐の三位一体だ。(8頁)
信仰による特定の祈りをすることができた。生き生きとし、全てを包み込むような祈り、1週間かそれ以上ぶりの、今までの辛苦の甲斐があったと言えるほどの祈り。(10頁)
働きの進展はほとんど全てといっていいほどに、村の〈霊的潮位〉によるのです。(13頁)
祈りの道へ、どうか私を導いて下さいと、はっきり願い求めることから始めることが良いと思っています。(22頁)
私たちは神から祈りを与えてもらわなければならず、神のみこころを知るために祈るべきです。(34頁)
こうして失意のうちに帰国を決心し、そのことを村人に告げました。ところがまさしくその出発の日に奇跡が起こったのでした。村人たちが、こぞってフレイザーの下に集まり、かれらの心の内を少しずつ明かし始めたのでした。信仰告白です。そしてその波は近隣の村々にも早速に伝わったというのです。
以上は成功例ではあっても、最終幕でそれが明かされるという一種のドラマのような筋書きにもなりました。そしてそれは、平時の祈りとも有事の祈りともいえるような状況の中から生み出されたものでした。
イ.「祈る人」になること
インドで活動した著名なキリスト教者マザー・テレサ(1910―1997年、マケドニア生まれ)は2016年列聖されましたが、彼女の言葉に次のようなものがあります。それは平時でも有事でも、祈りなさいと言っているようです。
祈りを唱える人ではなく、祈る人になりなさい。(注2)
祈る言葉に取らわれるのではなく、ぞっこん祈る世界に入り込みなさい、と解釈されます。列聖される人たちはまず間違いなく、このぞっこん組であろうと想像されます。彼女の言葉をもう少し確かめておきたいと思います(注3)。
*祈りについて
祈るために、仕事を中断する必要はないのです。仕事を祈りであるかのようにし続ければよいのです。(30頁)
祈りとは自分自信を神のみ手の中に置き、そのなさるままにお任せし、私たちの心の深みに語りかけられる神のみ声を聴くことなのです。(35頁)
愛はどこから始まるのでしょうか?私たちの家庭からです。いつ始まるのでしょうか?共に祈るときに始まります。共に祈っている家族は崩壊することがありません。(104―105頁)
*神への奉仕
大切なことは、たくさんのことをし遂げることでも、何もかもすることでもありせん。大切なことは、いつでも何に対しても喜んでする気持ちがあるかどうかなのです。貧しい人々に奉仕している時、私たちは神に仕えているのだと確信していることなのです。(70頁)
*正真正銘の信仰
もしも、信仰が希少価値になっているとすれば、世の中が自己中心的、利己的になりすぎているからなのです。正真正銘の信仰は惜しみない寛大さを伴うはずです。愛と寛容はいつも共に存在します。(76頁)
*神の技
自分に出来る限りの、最善の努力を尽くさなかった時(著者注:ここは努力を尽くしても、とも読めるが引用は原文のまま)、失敗したとしても失望することはないでしょう。成功も私たちの力によるものではありません。結果はすべて神に委ねるべきで、私たちは心底から信じてそのような態度を取ることが大切です。(128頁)
*淋しさが本当の貧しさ
貧しさにはいろいろあります。経済的にはうまくいっているように思われる国さえも、奥深いところに隠された貧しさがあるのです。それは見捨てられた人々や苦しんでいる人々が抱えている極めて強烈な淋しさです。(158頁)
*本物の宗教
ヒンズー教の信徒の男性が、カリガート(カルカッタ近く)にある私たちの「死を待つ人の家」を訪れた時、私は一人の病人の傷の手当てをしていました。黙って私の仕事をしばらく見た後、その人は言いました。「あなたにそういう仕事をする力を授ける宗教は、本物に違いない。」(170頁)
終り
注1:ジェームズ’アウトラム’フレイザー『信仰による祈り』イーグレプ、2014年。58頁の経験録の小冊子。しかし大部な研究書にも劣らぬ迫力がある。
注2:https://ameblo.jp/hiroo117/entry-12090335871.html 2021年11月10日検索。
注3:マザー・テレサ『マザー・テレサ 愛と祈りのことば』渡辺和子訳、PHP文庫、2000年。
イスラームの利他主義(水谷 周)
利他主義は利己主義と対置される言葉で、自己の利益よりも他者の利益を優先する考え方として知られます。厳しい時代となるにつれて、この考え方の価値が高まると言えるでしょう。仏教やキリスト教の脈絡でも多く語られていますが、ここでは余り言われることのないイスラームの利他主義について取り上げます。
一般的な定義としては、次のように言われます。
「行為の目的を他人に対する善におく倫理学上の一学説であり,一般に利己主義と対照される。この言葉はオーギュスト・コント(フランスの社会学者、1798―1857)によって採用されたが,ある意味では東西の主たる倫理観はこの利他主義を内包しているといえる。この「善」の基準を何に求めるかによって利他主義もいろいろと区別される。それをそれ自身多様な解釈を許す快楽に求めるとすれば,功利主義となり,人格という視点に立てば人格主義に結びつく可能性もある。この意味で利他主義は,一義的には決定しがたい幅広い思索を含んだ倫理学説であるといえる。」(ブリタニカ国際大百科事典)
いずれにしても、造語としての利他は近代の産物と言えます。それが日本に持ち込まれた際には、他人を思いやり、自己の善行による功徳によって他者を救済するという意味を持つ仏教用語の「利他」が当てられたということです。従って仏教であれ、キリスト教であれ、近代的な意味の利他の教えが含まれているという時には、時代を遡ってその教えは古典にも見出しうると言っていることになります。まず初めに確認しておきたいことは、イスラームも同様であるということです。
イスラーム初期の原典には、利他という用語は一度も出てきません。さらには中世の倫理道徳書にも登場しません。欧米流の議論や術語がイスラーム世界にも持ち込まれた後の、近代的な現象の一つなのです。そしてその教説は、イスラームの原典にも見出せるということになります。ただし利他の教えそのものの重要性と適用範囲の大きさに鑑みて、イスラーム世界でもすっかり市民権を獲得した言葉になっています。
2.とある現代イスラーム説教師の語り口から(ムスタファー・アルスィバーイー『われわれの社会道徳』ダマスカス、ダール・アルサラーム社、2005年。22—26頁。本説教は、1954年3月7日に行われた。)
アラビア語で利他主義のことは、イーサールと言います。それは好む、優先するという意味の動詞でアーサラという言葉がありますが、その名詞形です。他方、利己主義のことは、アナーニヤといいますが、それは自分という言葉であるアナーから派生した言葉です。
イーサールは、倫理的にも法的にも称賛されます。享楽を戒め、安楽を求めるのではなく苦労をいとわず、満腹ではなく飢えをしのぎ、生に拘らないといった姿勢が尊ばれるということです。さらには取得するよりは与えることを重んじ、見える物よりは見えない抽象的な事柄に比重を置くので、善行の象徴であるといった評価もされます。法的には義務でもなく、禁止事項でもない部類に属する内容ですが、そのような自由な判断の認められる範囲は実に広大なものです。そこで各自の思索と判断が問われるということになります。
利他とは言ってもその中に利己が同時に含まれているという指摘もされます。お国のために殉死するのは、そうすることで自分の国の栄光に貢献するが、その栄光は自らの名誉でもあります。利他と利己のいわば表裏一体の関係は、一言では整理されません。
利他は犠牲という言葉と不即不離に理解されます。誰しも先祖の犠牲的な尽力の上に生活しています。そこで想起されるのは、預言者ムハンマドとそれに続いた教友や従者たちの忍んだ苦労です。彼らの命をはった犠牲のお陰で、その後のムスリム共同体が成立し、発展したということが強調されます。また同時に、現在のわれわれの仕事はこういった先祖の苦労を忍びつつ、その艱難辛苦の道を継続するということになります。そうすることで、後続の世代の先駆けになるということです。
一方現代社会には利己主義がはびこっているといえます。それは家庭内であれ、政治経済面であれ、あるいは工業、商業、農業といった産業面でも言えることです。そこでは利己主義があるべき人間の紐帯を切断していると言えます。断絶、分断、そして格差と差別につながります。そのような私欲と野望の跳梁や闊歩を抑制するために、今一度利他の教える高邁な精神を取り戻すべき時代ではないでしょうか。
預言者たちが多神教徒を逃れるために、マッカからマディーナに移住したときに、マディーナのムスリムたちが移住者に示した歓迎の諸行は、利他の原点のように見られます。それはクルアーンに明らかです。
「そして以前から(マディーナに)家を持っていて信仰を受け入れた人たちは、かれらのもとに移住した人を愛護し、またかれらに与えられたもの(戦利品)に対しても、心の中でも欲しがることもなく、自分自身に先んじて(移住者に)与えます。たとえ自分は窮乏していても。自分の貪欲をよく押えた人たち、これらこそ成功者です。」(59:9)
「またかれらは、かれ(アッラー)への敬愛から、貧者と孤児と捕虜に食物を与えます。(そして言います)わたしたちは、アッラーの尊顔(喜び)のためにあなた方を養いますが、あなた方からは報いも感謝も望みません。」(76:8,9)
3.参考
徳目は常にそうですが、たとえ自分が傷ついてもその徳目を順守するかどうかが問われています。そうするためには、常にその徳目を学習しておく必要があるでしょう。利他の言葉をもう一度玩味したいものです。2020年、コロナ対策の10万円が特別定額給付金として全国民に支給されましたが、20歳代の若者の37%が寄付に回したとのこと。それは各世代を通じて一番の高率でした。日本社会にも望みがあるといえるでしょう。
終り
日本の清貧とイスラームの禁欲(水谷 周)
*目標:清貧は、所有する物や出世などの社会関係も削ぎ落して、裸の本来の自己を見つめ直すこと、そうすることにより自然のあり方と一体になり、より広く大きい自分を見出すこと。禁欲は、篤信行為と禁則の間にある取捨選択が自由な事柄について、適切に中庸のあり方として節度を守ること。それが安寧に導く、アッラーの道であるから。
*典拠:清貧は多数の文人などの言葉であるが、同様の精神は広く世界の宗教家などにも見出せる。他方、禁欲がクルアーンと預言者伝承に依拠するのは、イスラームの常套である。
*理想像:清貧は、山奥の草庵で独居する姿、そこで自然と触れ合い一体化する。禁欲は、過激さを避けて極端な孤立ではなく、日常生活の中での中庸の維持を目指す。ただし雑踏を避けたいとの気持ちは少なくない。
*現代社会の課題:清貧は現代日本では、積極的な側面が意識されている。他方石油資源に恵まれているイスラーム諸国は繁栄の頂点にあると言えるだろう。その中でも文化の底流としての禁欲の徳目は、その泉を枯れさせることはないだろう。現在は、節度という言葉が禁欲の代行を務めている感がある。
1.両思想の要点
*清貧の思想
「所有に対する欲望を最小限に制限することで、逆に内的自由を飛躍させるという逆説的な考え」、「それは自我の狭小な壁に閉じ込められないための工夫・・・。欲望や我執にとらわれていては、自己の外に遍満する宇宙の生命を感じることができない。そのために所有物を最小限にして、身を遍界生命に解放する手段・・・。」(中野161頁、202頁など)
所有する物や名誉などの社会関係もできる限り削ぎ落すと、自然のあり方と一体になり、より生き生きとして、広く大きい本来の自分の姿を見出せる。清貧の目指すところである。
*禁欲の定義
「アッラーに認められた行為には、篤信行為とそれとは関係のない自由な行為があるが、禁欲は後者の自由な行為を抑制すること」、「アッラーに認められない禁止された行為を回避するのは忌避と呼ばれる。」「禁欲は篤信と忌避の間にある。」(水谷57ー58頁など)
善意の行いはすべて篤信行為であり、悪意の行為はすべて禁止される。これは倫理道徳の世界であるので、イスラーム法上の諸義務(信仰告白、礼拝、喜捨、断食、巡礼の五行)や禁止事項(豚肉を食べ、アルコーツを飲むことなど)よりは広い範囲を対象としている。禁欲は、善意でも悪意でもない行為に関して抑制すること(食欲、権勢欲など)。過度な禁欲により安心を覚えるのであれば、それは新たな欲望を満たしているに過ぎない。適切で中庸な節制がアッラーの道であり、禁欲はそれを目指す。なお過激な禁欲は厳禁で、イスラームで聖職者を置かない理由は、彼らは厳格に走る恐れがあるからともされる。
2.思想の源泉
*清貧
多くの文人が参照されている。本阿弥光悦、鴨長明、良寛、池大雅、与謝蕪村、吉田兼好、松尾芭蕉などである。いすれも日本文化の列伝のようなものだ。こういった人々の考えや生涯から、共通項を取りまとめたのが、上記の清貧の思想ということになる。さらには、高名な禅僧道元の言葉「身心脱落」が引用され、またそれ程は知られていない禅僧寂室(1367年没)の「名利を求めず、貧を憂えず」が引用される(中野198頁、220頁)。
要するに多くの文人の巧みな表現の中にこの思想は見出されるということ。ただそれは、日本の諸宗教と衝突することはないし、むしろ強化されてきたということになる。なお文人だけにとどまらず、清貧の風習は庶民レベルでも大変普及してきたと明言されている。映画「24の瞳」で訴えられ言葉は、「清く貧しく美しく」であったことを想起している。
*禁欲
イスラームの禁欲の源泉は、あくまでクルアーンと預言者伝承である。以下、クルアーンの言葉を幾つか見ておこう(『クルアーン-やさしい和訳』監訳著水谷周、訳補完杉本恭一郎、国書刊行会、2021年。第5版。)。
「あなた方の現世の生活は、遊びや戯れであり、また虚飾と互いの自己顕示であり、財産と子女の多さの張り合いだということを知りなさい。・・・。真に現世の生活は、欺瞞の享楽です」(57:20)
「実際のところ人間は、自分の主に対し恩知らずです。それについて、かれ(人またはアッラー、あるいは両者)は証人です。また富を強く愛します。」(100:6―8)
「われらがかれら(マッカの多神教徒)の何人かに与えた、この世の生活の栄華へと、あなたの両目を(物欲しげに)向けてはいけません。われらは、それによって、かれらを試みました。あなたの主の糧こそ、最善で永続するのです。」(20:131)
虚飾と栄華は人に対する試みであり、求めるべきは主の満足であり、永続する糧である来世の楽園ということになる。つまりアッラーの道を求めること、求道である。
3.人生観
*清貧
山奥の草庵で独居して自然と触れ合い、そこでの自然との一体感が目標である
「むらぎもの 心楽しも春の日に 鳥のむらがり 遊ぶを見れば」(良寛)
「ませ(垣)に咲く 花にむつれて飛ぶ蝶の うらやましくも はかなかりけり」(西行)
「一生は、雑事の小節にさへられて、空しく暮れなん。・・・諸縁を放下(ほうげ)すべき時なり。・・・毀(そ)しるとも苦しまじ、誉(は)むとも聞き入れじ。」(吉田兼好)
小鳥の泣き声、あるいは花と蝶の心と一体になってこそ、人の本来であるとする。そのためには、雑事を離れ、「諸縁を放下」するとしている。なお、中世イタリアのアッシジで活躍した聖フランシスコは壁画に描かれて有名であるが、その中に小鳥に説教している図がある。その心境とも同根だとされている。
*禁欲
イスラームの諺には、「この世は雪で、あの世は真珠」というのがある。移ろいやすい現世と、永劫の来世を対比している。また「イスラームの美しさは、その単純さにあり」として、生活態度は控えめにし、過激ではない中庸や質素さを尊重する姿勢が強調されてきた。
禁欲とは平常心を保つことでもあるとして、アッラーの差配による災難に合う方が、その差配によらずに災難に合わないよりも、まだましだとの話もある。さらに、預言者伝承に見てみよう。(水谷60頁)
「人は大金である1000ディナール持っていても禁欲でありうるのかとの質問に対して、預言者の従者たちのように、それが増えても喜ばず減っても悲しまないという条件であれば、と預言者は回答された。」
預言者の従者たちは喜怒哀楽に惑わされず、平常心を失わず、彼らの矢が敵を撃っても小躍りせず、反対に彼ら自身が負かされても気落ちしなかったということだ。こうして禁欲は中庸であり、中庸は平常心をもたらすし、それは安寧となり、安寧こそはアッラーの道の道標であるということになる。ただし孤立した独居ではないが、市場の雑踏は避けて、静穏を求めるといった気持ちは、古典時代以来、当然強く働いてきた。逆に権力者や富裕層に媚びを売るあり方は、卑下されてきた。
なお禁欲という徳目は、謙譲、忍耐や誠実さなどの徳目とも連動している。イスラームのすべての徳目は、あたかもアッラーという中核に、たわわに実った一房の熟したブドウの実のようなものである。それらを単独で、あるいは孤立した格好では、本当には全幅を語ったことにはならない。
4.現代社会と清貧・禁欲
今では環境保護の観点から、自然の保全は意識が高い。自然への回帰である。グリーン・ライフの呼び声も小さくないし、持続可能な開発でもある。そうすると清貧な生活こそは、それらのモットーと合致している。恐らく清貧の立場からすれば、そういった風潮は一層高めて、人の生き方として自然との一体感を確認し、そうすることで自らの物欲、出世欲からの解放を意識的に目指すべきだということになるのだろう。
イスラームの歴史上も、禁欲の徳目は大きく取り上げられてきた。歴代の禁欲者列伝も何冊も編纂されている。正統カリフのアリーは、わざと自分の衣服に穴を空けて、みすぼらしくしたそうだ。また逆に、権力者からは遠ざかるようにとの警告も、精勤な学者たちからは出されてきた。これらの風潮は20世紀の石油ブーム以来、あまり社会の表面には出てこない。しかしそれは一時的な現象で、文化の底流を見失うべきではないだろう。日本でもバブル崩壊の時期を経てこそ、清貧運動が再燃したのであった。なお現在よく目にする用語は、節度である。それは従来、主として女性が貞淑であることを指す言葉であったのが、今ではより一般的に用いられているものである。その結果として、節度は禁欲という昔からの表現の代行を務めている感がある。
以上の考察は簡略なものに過ぎない。しかし実は多くのイスラームの抽象的な事柄を語る上で、それを日本語でする以上、相当な慎重さを必要としていることを示唆している。訳語の限界かも知れないが、互いの歴史や文化の距離が大きいほど、丁寧な扱いが求められる一例ともいえる。さらには、宗教関係の日本語には仏教用語が氾濫しているので、イスラームはそれらに依拠せざるを得ない難点もある。慈悲は大きなイスラームの概念だが、当然それは仏教とは異なる。またそれがキリスト教の博愛とも似て非なるものであるのと同様。異文化間に橋を架ける作業は、一日にしてならずということは再確認できる。
終り
日常の祈りーその1(水谷 周)
昔からの表現として、「困った時の神頼み」というのがあります。苦しいときや死の恐怖にさらされると、神仏を崇め始めるというのです。長い人生を歩んでいれば、これに似たような経験は大なり小なり誰しもするものでしょう。また世の中全体を通して見ても、災害などの惨状の場面には必ず祈りの姿が見られます。またその側には、僧侶や牧師さんと見受けられる人たちの活動も散見されます。こうして例えば、2011年の東日本大震災の後には、宗教復興の兆しを見出す人たちも少なくありません。
著者が感心する本は多いのですが、その一つに『祈りの現場』と題されたものがあります(石井光太『祈りの現場』サンガ、2015年。)。著者はフリーの作家ですが、国内外の貧困、医療、戦争、災害、事件など幅広いテーマで執筆している人です。同書で感心させられたのは、幾多の悲劇と向かい合う宗教者を忍耐強く取材していることの他に、そのような珍しい視点を維持して一書にまとめ上げたということです。その中に作家としてのただならぬ、一貫した信念を感じさせられたのです。
ただここで同書の話を持ち出した理由は、そこで取り上げられた各地の「祈りの現場」というのは、すべて日常的ではない状況ばかりだからです。東日本大震災、釜ヶ崎、刑務所内、伊豆大島土砂災害、そして広島での原爆と続きます。これらをまとめていえば、非日常的で異常な、いわば有事の現場であるといえるでしょう。そのいずれも、生と死という人間として究極に追い詰められた現場なのです。
窮状に至れば至るほど、祈りは熱気を帯びて、絶え間なくなり、それに立ち会う聖職者たちも全力投球になるのは自然なものとして誰にでも理解できます。他方それだけだと疑問が残るのは、それでは日常的な状況での祈りや聖職者たちの役割はどう考えるのかということです。それら平時の祈りは、小さくて軽いものなのでしょうか。このような問いかけに対する優等生的な回答は聞くまでもなく、すでに決まったようなものでしょう。つまり、それはそうではなく、祈りは何時であっても同様に重いものであり、人として必須なものであるということになります。しかし回答がただこれだけではあまりに短絡的です。以下ではその事情を、今回と次回の2回に分けて、もう一歩視野を広くして見ておきたいと思います。
<寺院の標語>
多くの寺社仏閣などの入り口に、張り出しで信仰の標語が掲示されています。それは時々変更されるものですが、最近、自宅近くのお寺の参道で著者が見たものに「日常の中の祈り、祈りの中の日常」というのがありました。この言葉の前半はまさしく平時の祈りを指しています。ところが後半に至ると世界は全く別物です。なぜならば、生活の中に祈りがあると言っているのではなく、祈りという営みの中に生活があるからです。
右の標語は一枚の大きめの白紙に手書きの達筆で記されていました。しかし出典などの記載は何もありませんでした。その寺院の住職さんのものかも知れないし、どこかそのような標語集から転用されたのかも知れません。でも出典はどこであるかは余計なことで、この言葉が伝えている重みこそを十分玩味し、自身の血肉の一部としたいという想いに駆られるものでした。
またもしその標語が住職さん自身のものであるなら、その方は相当の方だろうと思わせられました。深い思いを巡らせ、多大な人生経験を積まれた人で、同時にそれらが埋め込められた巧みな一言に見事に表現されているということになります。そう感じながら、入り口から境内に向ってそっと著者の頭は下がりました。
ちなみに同様な気持ちから筆者自身が以前に読んだ歌がありますので、この機会に再登場させておきたいと考えます。
幾山河 越え行く日々のありがたさ
わが身と心 慈衣につつまれ
この趣意は、毎日山あり谷ありだが、それを乗り越えて生きて行く自分の心身は、いつも慈悲の衣につつまれているといったところです。感謝、感謝の毎日ということになります。そして感謝は何といっても、祈りの中心的な要素ですから、これは毎日片時も祈りを忘れないということにもなります。やはり「祈りの中の日常」であるわけです。
特 集 儀礼の変容 対談 神田神社で考える神道の原点と未来(鎌田東二・清水祥彦/司会:弓山達也)
新型コロナウイルスの流行を契機に、宗教儀礼の簡素化がいっそう進行するとの懸念が表明される一方、オンラインでの宗教活動やバーチャルな参拝といった新しい儀礼のあり方にも注目が集まっている。
本対談では、宗教学者であるとともに日本各地の神社や山岳で新たな祭や神楽、独自の修験道を始めた鎌田東二氏と、「神田明神」として地域社会に親しまれ、伝統を受け継ぎながら、SDGs への取り組みや秋葉原のポップカルチャーとのコラボレーションでも知られる神田神社の清水祥彦宮司に、神社神道の過去と現在、そして未来をテーマに語っていただいた。
少子高齢化や過疎化、パンデミック、さらにはAI が人間の知能を凌駕するシンギュラリティといわれる時代の到来に、宗教はいかに対応しうるのだろうか。
(出典:『現代宗教2022 特集儀礼』公益財団法人国際宗教研究所、2022年1月刊)
信仰心蘇生のために その12 最終回(水谷周)
信仰心の維持と強化は、日常の雑事に紛れる中、強い希求の気持ちと明確な意識に基づくことが望ましい。この目的に役立つと思われる諸側面を無作為に記述する。広く人の心の傾きを念頭に置いて、一般論としての説明。なお本シリーズはこれが最終回になる。
心に迷いが生じて信仰を求め、信仰を得ればその迷いも霧散する。そして心には安寧が得られるので、それは不動であり、大船に乗った心地である。これらをまとめれば、信仰の心はバランスが取れているということにもなる。
人の心はどのようにして決まるのだろうか。それは理性も感性も、すべての作用の結果であり、あまりに複合的なので、『宗教学辞典』(東大出版会、1973年初版)などでも定義はされていない。できないのである。魂が生死にかかわり、精神は意思のあり方といった意味として受け止めることができる。そうだとしても、心は何とも無定形なものを指していると受け止められる。ただその無定形なものは存在することは間違いないので、その実態の呼称として心というものを持ち出すことになるのだろう。科学的な分析ではなく、極めて非実証的で非分析的であることをむしろ前提として用いている言葉である。
だからいくら人工知能AIが発達しても、心は不可侵なものとして存続することとなる。何とも扱いにくい実体であったとしても、それを否認して人は生きることはできないし、誰もそのような否認をしたいとも思っていない。ロボットになりたいと望んでいる人はいないということだ。
そこで心の実在を正面から求めつつ、その健全さを望むことが人の道であるということになる。それは正しい道、あるいはまっすぐな道といってもよい。まっすぐな道を正しく歩くのは、心がバランスを保っているからである。揺るぎなくも、過たない歩みである。それを望むという自然な心の働きがあるということは、裏から言えば、そのような正しい姿勢の歩みは放置しておいてできるわけでもなければ、誰にでもいつでも可能なものでもない、ということ。そこでそれは、希求して初めて獲得されるということになる。
そこで求道の必要性が説かれるし、それは日々の務めであり、目標でもある。こういったことをこのシリーズでは12回にわたって述べてきたので、読まれた方々にはもうこれ以上の説明などは不要であろう。千々(ちじ)に乱れ、ゆらゆら、ふらふらではなく、堅固にしっかりした歩みである。その歩みを大切にしつつ、過ごすのが人生ということになる。それには、人種、国籍、学歴などは一切関係しない。関係するのは、その人の決意と実行力だけである。
こういう次第が自然と自分のものとして飲み込める頃には、もう解脱の段階に達していると言える。そのためには、心を切り替えるべく、信仰世界への一瞬の投身が必要であり、そのような技は誰にでも天性のものとして賦与されていると多くの宗教は教えていると思われる。
信仰心蘇生のために その11(水谷周)
信仰心の維持と強化は、日常の雑事に紛れる中、強い希求の気持ちと明確な意識に基づくことが望ましい。この目的に役立つと思われる諸側面を無作為に記述する。広く人の心の傾きを念頭に置いて、一般論としての説明。全12本だが、毎月一本を順次掲載する予定。今回は、信心の基軸である絶対主に依拠するといういうことがテーマになる。
神であれ仏であれ、現世を超絶した存在を主と呼ぶこととする。主は全存在を統括、管理されており、人間はその一部に過ぎないという位置づけになる。そして主が始原であり永劫であるとすると、それ以上に確かなものはないので、それに人はしがみつくしかないという姿になる。
しがみつく姿は、数珠を握り締めるのもそうだし、十字架を手から離さないのもそうだ。阿弥陀像に結ばれた紐を死床で握っているのは、それで西方浄土に導かれるとの信仰からだ。イスラームでもアッラーの称名を数えるための数珠があり、日常生活でそれをいつも手にしている人を多く見かける。肉体的にしがみつくということと、精神的にしがみつくのとは完全には同じではないかもしれない。しかし肉体的にそうしていることは、精神のあり方を指し示しているとも見られる。
主にしがみつくことで、信心がゆるぎないことを示そうとしている。また握り締めている動作は、自分に対してもゆるがせにしないことを誓っているようなものだ。だからその効果は計り知れないし、それだけに宗教の如何を問わず採用されているのであろう。
ただ一つ注意したいことは、握り締めることは、伝統墨守で固陋な姿勢を取っているのではないということだ。この辺りは簡単ではない。じっと固まっているのではなく、しっかり握ることで常に自浄作用と新たな自分を発見する更新作用を伴っているというのが実情である。毎日が繰り返しと見えるとしても、その中では恒常的なリニューアルが並走している事実は見逃せない。そしてそのように、日々更新され、新たな発見に驚く自分がいなければ、それは因習と腐敗への道をたどることとなる。多くの宗教が衰える最大の原因ともなってきた。
このことはどの宗教にもある原典の解釈についても言えることだ。新解釈などと言うと軽率で安直な語感があるが、しかしそれは良い意味では、最も必要であり、その原典に新たな生命を吹き込む作業でもある。それは新時代の需要を満たすためかも知れないし、新情報に基づく内容かも知れない。もちろんそれは容易な作業であるはずもないが、やはり一世紀に一人くらいは新解釈を主張する指導者が輩出するくらいの、エネルギーと進取の気性が望まれる。
新規産業とさらなる利潤などと言うとなじみのある用語が並んでいるかもしれないが、宗教も精神界の産業であると言える。ただしそれは人の天賦の才覚である想像力・予知能力に基づくという意味で人間存在の本源に直結する産業であり、人種や国籍に左右されない、万国共通の資源である。いかなる資源も正しい活用をしないと、人類を崩壊させるという意味でも宗教も産業だということになる。
信仰心蘇生のために その10(水谷周)
信仰心の維持と強化は、日常の雑事に紛れる中、強い希求の気持ちと明確な意識に基づくことが望ましい。この目的に役立つと思われる諸側面を無作為に記述する。広く人の心の傾きを念頭に置いて、一般論としての説明。全12本だが、毎月一本を順次掲載する予定。
信仰は人の全身全霊を挙げての営みであるが、それを一言で言えば、新たな価値の世界に突入し、没入するということである。簡単には自分の気持ちの切り替えと言ってもよいだろう。さらに言えば、従来の日常世界のただの延長上にあるのではなく、隔絶して明澄で高度な感覚に支えられている。
こういう事態について、二つのことを特記しておきたい。一つは、新たな価値という意味合いである。それが意図するのは、同じ行為をしても異なる意義が付与されるということ。例えば、寄付をするにしてもそれが対人関係上の人道主義的な発想のものではなく、対絶対主のお布施や喜捨という用語で表される行為となる。あるいはすでにお布施をする気持ちは、寄付とは別物だということは多くの人の経験が物語るであろう。信仰世界では、それ固有の価値体系があるし、その中に浸ることで信仰世界がよりよく理解されるものである。
二つ目に特記されることは、この新たな価値世界に没入するためには、人の気持ちが整理されていて、踏ん切りが必要だということである。どちらの世界にいるのか、ふらふらとしているようでは、そのどちらでもないということになる。壺阪霊験記という歌舞伎の演目では、盲目の夫が妻に面倒を掛けることを苦にして滝壺に投身するが、それを知って妻も後を追う、しかし両名ともが奇跡的に一命をとりとめ、さらに視力を取り戻し、妻が相当な美人だということも発見するという筋書きである。命拾いしたのは、二人は熱心な観音信仰を持っていたから、ということになっている。この話で注目されるのは、滝壺に投身するということ、つまり全身全霊を挙げて、突入するという行為である。これこそは信仰に入る覚悟と決意と迷いのなさを象徴していると見られる。
新しい価値の世界という文字だけを追うとすれば、それは間違いである。得てしてそうなる恐れは、多くの場合にある。それは従来の価値観を脱する、離れる、捨てるということでもあり、その人にとっては深刻な革命行為である。もちろんそのような意識があるとは言えないケースも多いだろうが、その現象であることは変わりない。それが一瞬のショックかも知れないし、あるいは徐々に訪れるその時であるかもしれない。悟りが開けたり、啓示が下りたりする多くの場面で、そのような状況をわれわれは知ることとなる。
自分自らの信仰発起の瞬間はどうであったろうか。どのようであったとしても、それができるだけ不可逆的で、なおかつ安定的であることが望まれる。そのようであるかどうかは自分で決められる問題ではなく、天の配剤なので悩む必要のない事柄である。
信仰心蘇生のために その9(水谷周)
信仰心の維持と強化は、日常の雑事に紛れる中、強い希求の気持ちと明確な意識に基づくことが望ましい。この目的に役立つと思われる諸側面を無作為に記述する。広く人の心の傾きを念頭に置いて、一般論としての説明。全12本だが、毎月一本を順次掲載する予定。
この言葉はすぐに理解できそうだ。休んでいる暇はないということである。
むしろ日々というよりは、一瞬、一瞬が勝負だと思いたい。それほどに人の心は移ろいやすいからだ。常にあれやこれやで揺れ動き、それだけにいつ道を踏み外しているかおぼつかないのが普通である。そのためには、自分を監視するもう一人の自分が、すぐ側にいるという感覚が助けになるかも知れない。
心が真っすぐな状態かどうか、正しい道に沿っているかどうかを監視しなければならない。心の襞(ひだ)を探り、そこに変な皴(しわ)がよっていないかをチェックするのである。黙想でもいいし、瞑想でもいいし、それを常に心がけられるかどうかが、問われている。
こういう際に道標となるのが、道徳上の徳目である。誠実さ、慈悲心、忍耐、公正さ、節制・自己抑制、感謝などは、宗教のいかんを問わずに是認され、奨励されている美徳である。逆に悪徳も意識しておこう。虚偽、不正、強欲、恨み、嫉妬心、見せかけ、自惚れなどが挙げられる。これらの一つ一つを掘り下げるのは、やりがいがあるとは言っても相当に時間もかかる。そして問題は、深堀すればするほど、次の問題に突き当たるだろうということでもある。
もう一つ重要なのは、覚悟である。何の覚悟かと言えば、例えば誠実で正直であることで、不利になり、損をして、傷をこうむるときでも、嘘はつかないという覚悟である。調子のよいときに美徳を守ることは、それほど困難ではないし、誰しも常識的にその準備はあると考えられる。ところが大きな課題は、順調でなく、逆境にある時である。どうかすると「嘘も方便」という考えに走り、あるいは親しい友人さえも裏切ってしまうかもしれない。このように自らに被害があると分かっても順守できるかどうかが、分かれ道である。その覚悟がなければ、本物ではない。それはご都合主義に過ぎないということだ。
釈迦は王子の身分を捨てて修行の道に入った。山中鹿之助は戦いに臨んで、「神よ、われに艱難辛苦を与えたまえ」と言って祈った。克己の覚悟とか禁欲の精神などとも言われるが、より厳しい水準を求めるからこそ、磨かれるのである。「汝、己を知れ」という標語はギリシア神殿の正面玄関に掲げられていたそうだ。
自分にどれだけ厳しく当たれるのかは、その人自身が決めることだ。常人であれば、その水準に上下の揺れがあるのが普通だろうし、放っておけば緩んでしまう。そしてそれを悔いて、慌てて克己の精神を想い起こす。信仰の日々は、忙しいということである。
信仰心蘇生のために その8(水谷周)
信仰心の維持と強化は、日常の雑事に紛れる中、強い希求の気持ちと明確な意識に基づくことが望ましい。この目的に役立つと思われる諸側面を無作為に記述する。広く人の心の傾きを念頭に置いて、一般論としての説明。全12本だが、毎月一本を順次掲載する予定。
信心は互いに響くものとは、何を意味しているのだろうか。それはまず、文字通りお互いに共鳴し、共感するものだということ。確かに信仰は自らの心の営みであるが、それは一人芝居ではない。それは多くの人の心の働き同様、周囲に波を及ぼすし、また自分も周囲からその余波を受ける。
まず初めに言えることは、信心があり、またそれをさらに求める以上は、一人さみしく孤独感に浸っているのではなく、仲間と心を開き共に行動し、楽しむべきものだということである。それが信仰の一つの功徳のようなものである。またそうすることで、自らの安堵感が深まり、確かなものとなるだろう。
次いで指摘されるのは、人の信心のあり方はすぐに他の人にも看取されるということである。それはその人に責任があるということになる。だから他人との関係の中にある自分を、自分でいつも監視しなければいけないということだ。こんなことは言われなくても自明のことと思う人もいるだろう。しかしここで強調しているのは、信心も例外ではないという点である。
このように見てくると、人の心の動きは不思議な世界である。「目は口ほどにものを言い」という表現が昔から伝えられている。人の心を知るのは、言葉以外にも動作や仕草で十分な場合もあるが、やはり言葉になれば相当決定的だ。しかし言葉でも動作でもなく、目の動き、目線のやり方でも心の動きが推し量れるのだ。いや、言葉よりも言葉にならないそれ以前の所作の方が、率直に心を表すかもしれない。われわれは社会生活において、このように多様で、複雑なやり取りの中を泳いでいるということになる。
人の心の中でも、喜怒哀楽と言われる鮮明な感情は伝わりやすいことは、誰しも経験している。しかし人間はそれよりもはるかに次元の高い感性や情緒も享受している。信心は動物的な感覚よりは、遥かに高次元の感覚と思考の部類に属している。崇高な、そして荘厳な気持ちであるが、それもやはり人々に共有され、人々は共鳴するものだということになる。
ただし信心は、世の中の雑事にもまれてすぐに傷付き倒壊してしまう面がある。それは繊細で高次元であるので、なおさらそうである。ところがそれが仲間と共有されて、共感をもって享受され育成されていれば、かなり補強される。だから信心は一人さみしく育むのではなく、互いに信仰の兄弟姉妹になるのが正解ということになる。
人は見ればその心根が見て取れるもの。さらにそれを絶対主は、いつもどこでもご存じであるということが、信心の中軸にあることは間違いない。
神道からみた比叡山と天台本覚思想(鎌田東二)
比叡山は日本最古のテキスト『古事記』の中に出てくる。「大山咋(おおやまくひの)神(かみ)、亦(また)の名は山末之(やますえの)大主(おほぬしの)神(かみ)。この神は近(ちか)つ淡(あふ)海国(みのくに)の日枝(ひえ)の山(やま)に坐(ま)し、また葛野(かづの)の松尾に坐して、鳴(なり)鏑(かぶら)を用(も)つ神ぞ」というのがその記述だ。『古事記』は和銅五年、つまり西暦712年に編纂されたとされるので、それが事実だとすれば、奈良時代にはすでに山城国の比叡山(日枝山)が日本の神山の一つとして崇められていたことになる。
が、事実はそう簡単ではない。この章句は平安時代初期に、ある人物によって書き加えられた後日挿入記事ではないかと疑われている問題の箇所でもある。
この大山咋神がどのような神格であるのかは「鳴鏑を用つ神」とされるところから、音の鳴る矢を持つ、狩猟にかかわる神であることが推測される。近江や山城の国の山の威力を持つ「山末の大主」である「山王」の神。そこに、大和の国から最強の神山の三輪山の大物(おほもの)主(ぬしの)神(かみ)(大己(おほな)貴(むちの)神(かみ)ともされる)が勧請され、日吉大社の西本宮の神とされていくので、日吉大社は比叡山の神と三輪山の神の二つの最高神山の神々を祭る稀有の神社である。そこに最澄が一乗止観院を創建した。間違いなく、比叡山の神々、日吉大社の神々の加護を念じながらの創建であった。
この比叡山で、円仁の弟子の相応(831~918)の時代に天台千日回峰行が始まったと言われている。それが歴史的事実であるかどうかは定かではない。が、回峰行の始祖とされる相応と回峰行起源伝承には興味深いものがある。
それは、相応の行の発端に『法華経』の常不軽菩薩の精神と行動規範への賛美と追跡があったとされている点だ。そしてそれが、相応と同時代の安然(841~?)らの天台本覚思想の命題「草木成仏(草木国土悉皆成仏)」と共通する精神性を宿すと考えられる点である。
天台本覚思想は、すべてはすでにそのままで悟っている、仏であるという、万物仏の究極の肯定思想である。それが回峰行の精神とつながっている。

信仰心蘇生のために その7(水谷周)
信仰心の維持と強化は、日常の雑事に紛れる中、強い希求の気持ちと明確な意識に基づくことが望ましい。この目的に役立つと思われる諸側面を無作為に記述する。広く人の心の傾きを念頭に置いて、一般論としての説明。全12本だが、毎月一本を順次掲載する予定。
信仰する者の果実は安寧の心であるということは、前述した。泰然自若だとも言ったが、そのような漢語を用いないで経験的な表現が、ここでの大船に乗った心地だとも言える。小舟は波に揺られやすいし、下手すると沈没もしやすい。それに比べて、大船の乗り心地は動揺することもなく、時には船に乗っていることも忘れるほどかもしれない。
過去には船の大小に例えて、仏教の教えが区別されることもあった。仏教はインドからアジアの南と北に分かれて伝播された。南伝仏教を小乗仏教と呼び、北伝仏教を大乗仏教とも呼ばれてきた。つまり北伝の方が正しい教えであり、南伝のそれは誤りという意味なので、そのような呼称は北側から見てのものである。南伝はより個人の救済を強調するが、北伝のそれは社会的な救済を重視するといった区別がされることもあった。いずれにしても、現在はこの小乗仏教という呼称は用いられなくなり、南側も自らのことは上座部仏教、つまりお釈迦様の一番近くの席で教えを聞いていたという意味の用語で呼ぶこととなった。北側もこの上座部という呼び名を尊重して、小乗という侮蔑用語は避けることとなった。
堂々としていて不動の気持ちであるのが、大船に乗っているということであるが、思うに昔の小舟はよほど木の葉のように揺れ動かされて、沈みやすかったこともあるのだろう。今読んでいて大船の安心感がピンと来ないならば、小舟の危険性を思い浮かべると理解は早いのかもしれない。
しかし今一歩突っ込んで思いを巡らせるならば、実際大変な大船である、豪華クルーズ船で最近起こったことが、新型コロナ・ウイルスの感染であった。こうなると大船だから安心だとは言い切れなくなる。つまり大船は乗客数が膨大なので、別の危険性が潜んでいるということになる。火災も可能性が数倍に増大する。こういう事実はやはり無視できないので、信仰との関係でもこの同じ事実の裏面も忘れてはならないということになる。
信仰を持って安堵感に浸るのは、信仰の果実であり、信者の特権でもあるが、それに満足して無防備になることは許されないのだ。第一に信心は、壊れやすいガラスの城であることは前述した。またそのようなリスクは毎日、いや毎時間襲ってくるのが実情であるので、警戒心は不断のものでなければならない。言い換えれば、小舟は言われなくても用心するが、大船は意識して自らに注意喚起し続ける必要があるということになる。信仰心の実態に即して理解するならば、大船の方が慢心を起こしがちなので、危険度は高いのかもしれないということになる。これは新たな教訓としたいものである。
信仰心蘇生のために その6(水谷周)
信仰心の維持と強化は、日常の雑事に紛れる中、強い希求の気持ちと明確な意識に基づくことが望ましい。この目的に役立つと思われる諸側面を無作為に記述する。広く人の心の傾きを念頭に置いて、一般論としての説明。全12本だが、毎月一本を順次掲載する予定。
人が信仰を求めるのはどうしてだろうか。それは考えてそうなるのではなく、自然な心の傾きなのである。恣意的ではなく、作為的でもなく、無辜な赤子の心なのである。
そのような人の心はいつも将来不安に悩まされるようにできている。仏教ではそれを、生老病死の悩みとしてまとめている。人生は悩みに満ちていることになるが、その根本原因はまだ見ない将来を想像する能力が賦与されているからである。
先を想い悩み、望み、絶望し、期待に胸を膨らませるのである。これはそうしようという意思があるからではなく、文字通り赤子の心理であり、成人の心理なのだ。生きるということの裏面は、想像世界にどう立ち向かうかという課題と取り組むことともいえる。つまり想像することが、人生の重要不可欠な反面だということになる。
不可避的に想像する、そうすると不可避的に悩み、不安に駆られ、生きて行く道標を求め始めるのである。そうすることは、繰り返すが、人間として自然な、天然の反面なのである。だから宗教信仰は、人の半分であると言いきれる。しかも誰しもそうなのである。そう思っているかどうかは別問題であり、何かを信じようとし、何かに縋り付いているのが、人の恒常的な姿なのである。だれしも自分を、また周囲の人を振り返ると、そういう実態が浮かんでくるであろう。
そこで信心を持つという意識があるかどうかとは別問題として、確信、信念、信条といった用語も別問題として、それらはすべて人の心が求めるところの確かに信じることのできる一群の考え方ということである。それらが与える果実は、言うまでもなく自分としてのしっかりした考えや、思想である。間違いないと思えた時の安堵感は、誰しも自分の身で経験があるはずだ。この心理状況を称して、安寧と呼ばれる。
安寧は安心と区別される。安心は不安感のないことであるが、安寧はそれよりも一段と格が上になると言えよう。安寧は、不安があっても動揺しない心持ちだからである。不安を不安として受け止められるし、それをも前提として心のバランスが崩されないレベルなのである。仏教でいうとそれは、悟りを開いた、さらには涅槃の心境に達したとも表現されるものである。
この信心の段階は、不動な心境とも言える。泰然自若とも言える。それは自然であり、人間界の浮き沈みを悠然と受け止め、その人の身体全体は全宇宙のうねりの一端として、無駄な抵抗や人為的な所作を慎み、そこに高次な楽しみを見出すことが可能となる。そしてそれが信仰の真の果実を得るという意味なのである。それこそは高度な幸福であり、人の生涯を通じての、最高にして究極の到達点と位置付けられるのである。
信仰心蘇生のために その5(水谷周)
信仰心の維持と強化は、日常の雑事に紛れる中、強い希求の気持ちと明確な意識に基づくことが望ましい。この目的に役立つと思われる諸側面を無作為に記述する。広く人の心の傾きを念頭に置いて、一般論としての説明。全12本だが、毎月一本を順次掲載する予定。今回は、「信仰は自らの務め」。
この言葉は二つに分けて考えられる。第一には、前半の「自らの」という部分である。信仰は人に言われてするものではなく、自分自ら求めるものであることは、ほとんど自明のように聞こえる。誰も人に言われて、強いられて信仰に入る人はいない。そのようなきっかけが人によって与えられることはあるとしても、それは自らが欲していてそれが刺激されて、促されているのである。だから自らの判断と願望が基本にあることは、分かりやすい。
またさらに少々複雑にとらえるなら、それは自ら発するだけではなく、自分自身に属するという意味でもある。つまり他人事ではなく、自分の問題であり、課題であるということだ。信仰による救いも、それに欠けるための懲罰も、自分が背負う問題であるということ。他の人にそれを擦り付け、または責任逃れはできないのだ。それだけに自分自身の世界をしっかり守るような感覚を覚えるものであろう。
他方、上の言葉の最後にある「務め」という部分は、注意を必要とするだろう。務めというと普通は、仕事であり、義務的なものを想定する。では信仰は義務的なものなのだろうか。ここでの答えは、その人にとっては義務的であるということになる。つまりそれは任意で、随時に儀礼を行うと言った気ままなものではないということである。それだけ自分を縛って、その規範を従順に順守することが求められるのだ。
自分の務めである以上、その出来、不出来の成績は、自らが付けることとなる。それは自分が一番よく知っているし、それ以上に崇拝の対象である絶対の主が隅々までご存じであるという意識が充満しているはずである。「お天道様が見てござる」と昔から日本では言い古されてきた。
これが畏怖するという内容である。崇高なものに畏怖し、その荘厳さを味わうといった場面が、現代の日本で巡り合わすことはほとんどないのだろう。夜空の満天の星が眺められれば、それに近いものを実際に目にすることができるくらいである。それほどに現世を越えた超絶した諸物や思想に恵まれていないということにもなる。「務め」の一言には、このような荘厳な響きを感じなければいけない。日常的な義務感の世界ではなく、それは超絶者との関係での人間、信者の果たすべき責務、お仕事であり、当然の勤行なのである。
この「務め」は、絶対者との信頼関係の基礎であり、出発点であり、自分自らの存在の原点を確かめる所作ともいえる。それなくしては、礎石なしの建造物である。その危うさは、試す必要もないと言わねばならない。
信仰心蘇生のために その4(水谷周)
信仰心の維持と強化は、日常の雑事に紛れる中、強い希求の気持ちと明確な意識に基づくことが望ましい。この目的に役立つと思われる諸側面を無作為に記述する。広く人の心の傾きを念頭に置いて、一般論としての説明。全12本だが、毎月一本を順次掲載する予定。
信仰の前には男女、老若、大小、高低、肌色など区別はない。あるのは信心の確かさ、篤さの別だけである。これは当たり前のように響いたとしても、思い返すと人間関係や人の評価をこのような基準で見直すことは、当たり前ではないことに気付くだろう。それだけわれわれは、それ以外の多くの属性によって人を判断することに慣れきっているからだ。
男女ともその外見で、イケメンかどうか、美人かどうかが取り上げられることが多い。その人の心の在り方、ましてや信仰心の篤いかどうかなどといった秤は、通常誰も持っていない。あるいはお金持ちかどうかも、多くの場合人を判断する目印であり、その人との付き合い方の基本となることも少なくない。
それではある人の信心の篤さをどうやって知ることができるのか。それは筆者の経験によるとあまり説明を必要としないことであり、あるいはあまり言葉にできない部類のものである。いわば直観である。その人の目線であるとか、その人の言うことではなく、言い方であるとか、逆にそのヒントは有り余るほどある。それを直観で察知できるかどうかは、自分の側の心に篤いものがあるかどうかにもかかっているともいえる。自らにそのような心の準備ができていないで、相手の宝を見出すこともないということになる。
では信心があるという場合に、それに大小、高低の差があるのだろうか。それは素直に考えてみて、存在するという結論であろう。何事にも熱心な人とそうでない人がいる。あるいはもっと細かく言えば、特定の人でも熱のこもるときと、そうでもないときとがある。これも不思議はないことで、調子の良し悪しは誰でも日々変化している。
以上を通じて見失いたくないことは、信仰心はいろいろの態様や強度があるとしても、結局すべての人の信心は平等であるという点である。つまりその質において、完全に平等なのである。上下も左右もない。宗教施設では寄付金額によって信者の名前に大小や高低の区別が付けられている風景はよく見受けられる。これは現世的な心情と信仰上の基準との妥協というべきものである。本来は全員同列であるとするのが、信仰のあるべき理解なのである。
研修会や勉強会の信者の座り方も、上下も何もない。全員が全く平等であるとのこの世でも珍しい経験をする良い機会でもある。人はなかなか目に見えないもので判断し、自分の言動を縛ることはできないものである。しかし信仰心は誰のものであっても、貴重な輝く真珠のようなもので、平等であるという意識を堅持することで、自分の信心も大切にしたいと思われることである。
信仰心蘇生のために その3(水谷周)
信仰心の維持と強化は、日常の雑事に紛れる中、強い希求の気持ちと明確な意識に基づくことが望ましい。この目的に役立つと思われる諸側面を無作為に記述する。広く人の心の傾きを念頭に置いて、一般論としての説明。全12本だが、毎月一本を順次掲載する予定。
近年宗教の経典を巡るシンポジウムがあったが、その際に次のような話を水谷よりした。その日は都内が雪で白くなったが、寒い中を参加した人には善行に対する恵みや報奨があると考えるのは当然、しかし安全や健康を考えて欠席した人も種々悩んで尽力して決断したので、やはり報奨があるのである。
そこで結局どちらでも報奨があるのだと言うだけであれば、それは現世的な判断である。あるいは、人は自分の判断で進退を自由に決めて良いという理解に立つのであれば、それは法律的な発想である。そうではなく、いずれであっても最善の尽力をしたかどうかの心のプロセスが、信仰上の問題なのである。
恵みや報奨の有無やその大小は主や神仏の専権事項であり、善行への決意と実行が信心の領域なのである。そこで日常的で即物的な世界とは異次元の信仰世界があり、その中に入りきることが信仰心というものであるということになる。それを一般論として言えば、固有の価値体系としての宗教世界そのものが念頭にあり、それで心が充満されていることが必須条件だということになる。
以上多少の事例に過ぎないが、経典を読んで信仰を強めるとともに、信心がなければその啓典の意味がよく汲み取れないということにもなる。信仰とは薄いガラスの城のように壊れやすいものだ。それは地震大国の日本だからではない。物欲が横行し、見えない諸価値をないがしろにし、人の心や魂を語ることはまずないという、この国の劣悪な精神的環境だからである。
さらに言えば、信心というものはそもそも、それ自体日常の迫りくる多くの圧迫と攻撃の下で、何時も潰されそうな運命にあるということだ。荘厳さと崇高さを伴う信仰という高次な精神的営みは、やはり繊細なものだということにもなる。それだけに、迷いと過ちの道ではなく、正しい道を歩みたい、そして人に優しく親切でありたいという強靭な求道の精神がなければ維持できないものだ。逆に正しい道にあることの有難さは、言葉に尽くせない。そしてその心境の安らかさも格別のものということである。
信仰心はいつも変化している万華鏡のようなものだけに、壊れやすいガラス製だということも覚えておくとためになる。それを前提にいつも自省し、自らを顧みる必要がある。そしてそのような習性を付けておくに越したことはない。それは電車の中にいても、会食の席でも、少々工夫すればできることである。現代日本の生活の中でも十分に実践可能なのだから、こんなありがたいことはない。
信仰心蘇生のために その2(水谷周)
信仰心の維持と強化は、日常の雑事に紛れる中、強い希求の気持ちと明確な意識に基づくことが望ましい。この目的に役立つと思われる諸側面を無作為に記述する。広く人の心の傾きを念頭に置いて、一般論としての説明。全12本だが、毎月一本を順次掲載する予定。
現代はストレスの時代だと言われたりする。人には想像力が賦与されているので、今ある自分以外の姿を描いたり、願ったりするのが常となった。それは夢、理想、願望などの形をとる。またそれは祈りでもある。この現実と空想との差違が、あらゆる悩みや苦しみの根源となる。しかもそれが常であるから、人はなかなか救われない。
ではこの差違がどうして苦しみの原因になるのだろうか。それは希望通りに行ってほしいし、そうなりうると考えるからである。両者間にはいわば、天と地のギャップが存在していることを認める必要がある。希望を述べることと、それが実現することとは別次元の話であり、この次元を無理やりに、あるいは無視して、垣根を乗り越えることは事の性質上できないのである。
祈る対象は主や神仏であるとして、祈りを上げる行為はそれで完結している。つまりお願いしたのであるから、そこでピリオッドが打たれるということである。それとその実現、または非実現は、別のいわば現実世界の事象である。そこで実現しようがしまいが、まずはそのような結果を授けられたということについて、人は主の配慮に感謝することになる。無視され忘れられていないからである。
しかし望み通りでないとすれば、やはり不満となるのであろうか。感謝をして同時に不満を覚えるということは、通常は矛盾であり、同時並行には生じないものである。実現かどうかの問題は、当面は現世の諸原因に基づく結果であり、そこでは不満よりは、さらなる自らの尽力を図り、最善を尽くすことしか残されていないのである。それは自らの非力の反省、悔悟かもしれないし、逆に明日への活力の源泉になるのかもしれない。
あの世との交流で祈るという行為と、現世の実現、非実現という事象を混同したり因果関係で結び付けたりすることは、人間の犯す過ちであり、認識不足ということになる。この微妙な関係を了解してこそ、初めて祈りの正しい位置づけと役割も理解されるし、実現しなくても感謝は忘れずにさらに一途に邁進し尽力するという、正しい姿勢が生み出されることとなる。祈ったということは、主に対してお願いしたのであり、お願いしてあるということで一つの仕事をしたという、安堵感や安心感も覚えるものである。保険を掛けてあるという比喩も出てきそうだが、それは主の配剤をお願いしてあるという保険である。だから失念されることはないだろう、という保険である。主の配慮ほどありがたいものはない。それは総合的であり、無限の時間幅の中での最高の配慮である。
正しい信仰はストレスを解消してくれるはずである。それは救われるという意味であり、信じる者は迷うことなくますます信仰一途の日々を送れることとなる。
Shintō and Japanese Civilisation(Toji Kamata)
The development of civilisation requires, for its material basis, increase in production of food and other goods, means of transport and transportation networks for moving these products, and innovation in, and sharing of, the technologies that support these. Laws, record-keeping and writing are also needed to enable the smooth operation of these large-scale systems. Above all, however, in order stably to maintain these in the long term, a religion or world view is needed which provides the people living there with spiritual stability. Accordingly, in any consideration of the form and history of Japanese civilisation and its characteristics an examination of its religion is of great significance. It was in the seventh to eighth centuries CE, the time of the establishment of the ritsuryō
system, that what we might call the conditions of civilisation, the establishment of a powerful authority and differentiation of classes, the establishment of a legal system, the construction of gigantic buildings, improvement of productivity and development of transportation networks, the establishment of cities, the use of writing and publication of documents, and the establishment of a religious system, were put in place as a system in the Japanese islands. Specifically, we might call the reigns of Emperor Tenmu (r. 673-686), Empress Jitō (r. 690-697), Emperor Monmu (r. 697-707), Empresses Genmei (r. 707-715) and Genshō (r. 715-724) and Emperor Shōmu (724-749) the age of the establishment of Japanese civilisation.
1. The beginnings of Japanese civilisation
The development of civilisation requires, for its material basis, increase in production of food and other goods, means of transport and transportation networks for moving these products, and innovation in, and sharing of, the technologies that support these. Laws, record-keeping and writing are also needed to enable the smooth operation of these large-scale systems. Above all, however, in order stably to maintain these in the long term, a religion or world view is needed which provides the people living there with spiritual stability.
Accordingly, in any consideration of the form and history of Japanese civilisation and its characteristics an examination of its religion is of great significance.
It was in the seventh to eighth centuries CE, the time of the establishment of the ritsuryō system, that what we might call the conditions of civilisation, the establishment of a powerful authority and differentiation of classes, the establishment of a legal system, the construction of gigantic buildings, improvement of productivity and development of transportation networks, the establishment of cities, the use of writing and publication of documents, and the establishment of a religious system, were put in place as a system in the Japanese islands. Specifically, we might call the reigns of Emperor Tenmu (r. 673-686), Empress Jitō (r. 690-697), Emperor Monmu (r. 697-707), Empresses Genmei (r. 707-715) and Genshō (r. 715-724) and Emperor Shōmu (724-749) the age of the establishment of Japanese civilisation.
It was in the reign of Emperor Tenmu, for instance, that the Ise shrine took shape, and it was in the 10th month of 690, at the start of the reign of Empress Jitō, that the regular rebuilding of the sanctuary and transfer of the deity took place for the first time. The functioning and continuation of such a large-scale ritual system is itself witness to the establishment and continuity of Japanese civilisation.
The founding of the Fujiwara capital, the building of which began in 690 and to which the court relocated from the palace of Asuka Kiyomihara four years later in 694, also in the reign of Empress Jitō, saw the establishment of the first imperial capital built on the continental grid pattern, another highly important event. In 710, in the reign of Empress Genmei, the capital was moved to Heijōkyō or Nara, and the year 712 saw the compilation of the Kojiki chronicles, followed eight years later in 720 by the compilation of the Nihon shoki. Thus, the 30 years from 690 to 720 can reliably be regarded as the years in which the fundamentals of Japan’s system of civilisation were established.
In 743, in the reign of Emperor Shōmu, the imperial edict for the construction of the Great Buddha statue of Tōdaiji temple was issued, and a decade later, in 752, the ‘eye-opening ceremony’ was held to mark its completion. This, too, is evidence of the strong and clear incorporation into Japanese civilisation of state-sponsored Buddhism. The 60-odd years from 690, when the first transfer of the deity of the Ise shrine took place (state-level Shintō ritual) to 752, the year of the eye-opening ceremony of the Great Buddha of Tōdaiji (state-level Buddhist ritual) can thus be seen as occupying a position as the period of the establishment of Japanese civilisation including the system of coexistence and complementarity of Shintō and Buddhism. In the ensuing 1,300 years, Japanese civilisation has maintained a strong continuity, at least in its shrines, temples, and emperor system. This long-term continuity would seem to be a Japanese characteristic not seen elsewhere in the world.
2. Geological basis for diversity of Japanese civilisation in tectonic diversity of the Japanese islands
What is this fundamental characteristic of Japanese civilisation? I see this in ‘diversity’ on a number of levels.
This diversity is exhibited firstly in the ‘tectonic diversity’ of the Japanese islands, which uniquely are situated at the convergence of four plates; secondly in the ‘biological diversity’ of the flora and fauna which developed there; thirdly in the ‘cultural diversity’ brought to these isolated islands on sea currents; and fourthly in the ‘diversity of deities’ of the religious concepts at the core of this culture. We can refer to these collectively as ‘the diversity of Japanese civilisation’.
In the Kojiki chronicles compiled in the early eighth century, this ‘diversity of deities’ was called ‘yahoyorozu no kamigami’ or ‘eight hundred myriad deities’. Of course, by the eighth century, not only the belief in the kami, the deities of Shintō, given shape in the form of Shintō shrines, but Buddhism, Confucianism and Daoism, embodied in temples and priests, had also been incorporated as constituent religious elements of Japanese civilisation. Moreover, the syncretism of kami and Buddha, a manifestation of this religious diversity, had already begun (1). Japan has taken this ‘diversity’ as its national character.
Japan is an archipelago of islands surrounded on all four sides by sea. The Japanese archipelago as we know it today came into being about 12,000 years ago. At the end of the last ice age, when the North Polar ice-sheet started to melt, and the sea-level rose, what had until then been a peninsula connected to the Eurasian land-mass became an island completely surrounded by sea, and the Japanese archipelago came into being.
This time marks the outset of the Jōmon Period, whose ceramic culture is said to be the oldest in the world, and the beginnings of the formation of the characteristic environment and culture of the Japanese archipelago. Japan’s natural environment has a number of special features. First, as I said before, it is a series of islands surrounded on all four sides by sea. In other words it has the natural features of an island nation. Second, the Japanese islands are volcanic in origin. The Japanese archipelago is situated in a geologically unusual region at the convergence of four tectonic plates, the Pacific, North American, Eurasian, and Philippine plates. This means there are frequent volcanic eruptions and earthquakes – in fact it is no exaggeration to say that the whole Japanese archipelago is constantly shaking. This throbbing archipelago is described in the Kojiki as ‘drifting like a jellyfish’. Third, as a result of the folding movement caused by the volcanic activity and the collision between plates, the mountains are mostly very steep, and 70% of Japan’s land area is mountainous and forested. Consequently there are a large number of clear-flowing rivers and streams and marshlands, and this fact eventually gave rise to a large number of water-related beliefs and a distinctive culture of water.
So Japan was an archipelago of water, surrounded by an abundance of both seawater and fresh water. This is why later, at the time that agriculture was imported from the continent, Japan came to be called Toyoashihara-no-mizuho-no-kuni: “the land blessed by ears of rice and water where reeds grow in profusion”. It is worth mentioning that in the Kojiki, Japan’s oldest extant literary work, which was compiled at the beginning of the eighth century AD, we find two ancient names by which Japan is known, Ōyashimaguni: “the land of eight great islands” and Toyoashihara-no-mizuho-no-kuni, whereas by the time of the Nihon shoki, Japan’s first official document compiled a few years later, the country has come to be referred to by the single name: Hi-no-moto: “source of the sun” – the same as today’s ‘Nihon’.
In the eighth century then, Japan comes to be known as Hinomoto or Nihon, but hi means fire as well as sun, and this “land of the sun” was also a “land of volcanoes” or a “land of fire”. We can see the vestiges of this older meaning in the ancient name for Japan’s south-western island, Kyushu, which was known as Hi-no-kuni, “land of fire”.
It is clear, then, that as well as being a land of water Japan was also a land of fire and a land of the sun. Indeed Japan’s natural features find expression everywhere in the names given to its islands and provinces. There is a traditional idea in Japanese Shintō that “fire and water” – represented by the syllables ka and mi, can also be read as kami – the gods, and the idea that a sacred energy was manifested in the natural generative powers of fire and water has come to be an important Shintō tradition.
Fourth, Japan’s forest cover can broadly be divided into two types, the beech and oak forest indigenous to northern latitudes, and the glossy-leaved forests typical of the southern regions, but both types of forest have excellent powers of water-retention and the water they release into streams is rich in nutrients which, together with minerals from the soil, find their way into the produce of the sea, the mountains, the rivers, and the fields. In other words they have given rise to an ecosystem that supports a rich plant life and provides an abundant supply of food. The Kojiki calls this natural power of fertility ‘musuhi’, written in the Nihon shoki with characters meaning ‘spirit of generation’.
We can point to the above four characteristics, then, as the salient natural features of Japan. The natural features of the Japanese archipelago are the basic foundation on which the beliefs of the Japanese have been built up. Their beliefs and view of the universe could not have come into being independently from the natural features of the land, and Shintō, as the expression of their beliefs and consciousness, could not have arisen either.
3. What is ‘Shintō’?
I should now like to address the question ‘what is Shintō’.
Nishida Nagao, Umehara Takeshi, Ōta Ryū, Kobayashi Tatsuo and Kamata Tōji see the origin of Shintō in the Jōmon culture. The Jōmon archaeologist Kobayashi Tatsuo, for example, argues that ‘the traditional Jōmon spirit is inherited uninterruptedly through the Yayoi and Tumulus periods to the ancient state’ and ‘the establishment of shrines can be traced back to such a deep-rooted tradition’ (Kamata Tōji, ed., Nihon no seichi bunka – Samukawa Jinja to Sagami no kuni no kosha [The culture of holy places in Japan: Samukawa Jinja and old shrines of Sagami Province], Sōgensha, 2012). By contrast, professors at universities specialising in the study of Shintō such as Anzu Motohiko and Ueda Kenji, emphasising the importance of agricultural and court ritual, maintain the view that the origin of Shintō lies in the Yayoi Period.
Both of these views have good arguments, and it is not possible to say which is correct. Nevertheless, it seems beyond doubt that the concept of ‘kami’ in the Jōmon Period flowed into, and blended with, the ‘eight hundred myriad kami’ summarised in the eighth-century Kojiki and Nihon shoki.
In reply to the question, when was this Shintō established, we can say that this took place in the seventh to eighth centuries, the time of the establishment of the ritsuryō system, as stated in Chapter 1. The reigns of Tenmu and Jitō, in particular, marked an epoch, and the grand designer, according to Ueyama Shunpei and Umehara Takeshi, was Fujiwara Fuhito (Ueyama Shunpei, Tennōsei no shinsō [Deep layer of the emperor system], Asahi Shinbunsha, 1985, Umehara Takeshi, Ama to tennō [Ama and emperor], 1991).
Clearly describing ‘Shintō’ is not easy. The first reason for this is that Shintō has no clear teaching or doctrine. Because of this, it is sometimes said that ‘Shintō is a doctrine-free religion’, and while this is not entirely wrong, this does not mean that there is nothing there at all. There are shrines, and there are festivals. There are also classical writings such as the Kojiki, Nihon shoki, Kogo shūi and Sendai kuji hongi which record myths and traditions. While it is true that there is no clear doctrine, there can be said to be a kind of ‘latent doctrine’ here.
By contrast, Buddhism has clear doctrines. The ‘three seals of the Dharma’ (all things are in a state of incessant change, all things lack inherent identity, nirvāna is perfect tranquillity); the ‘four noble truths’ (the truth of suffering, the truth of the arising of suffering, the truth of the cessation of suffering and the truth of the path); the ‘noble eightfold path’ (right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration); the twelve ‘nidānas’ (ignorance, formation, consciousness, name and form, six senses, contact, feeling, craving, clinging, becoming, birth, old age and death); these can be said to be essential or fundamental Buddhist doctrines. On the basis of these teachings of Shakyamuni Buddhism or early Buddhism, the ontological and epistemological theories of Mahāyāna Buddhist schools such as the Mādhyamaka or Chūkan school and the Yogācāra or Yuishiki (Consciousness-only) school emerged, and further there developed the systems of theory and practice (rituals) of esoteric mantra or shingon and mandala. In this sense, Buddhism can be said to be the totality of contemplation and practice resulting from the input of massive energy into tireless doctrinal innovation.
In comparison, Shintō doctrine is like a candle in the wind, and we can hardly be sure that there even is such a thing, and yet the fact that such an unsure ‘latent doctrine’ has stayed alive so tenaciously as the core of Japanese culture aroused the admiration of Lafcadio Hearn, who wrote:
‘Buddhism has a voluminous theology, a profound philosophy, a literature vast as the sea. Shintō has no philosophy, no code of ethics, no metaphysics; and yet, by its very immateriality, it can resist the invasion of Occidental religious thought as no other Orient faith can’ (Capital of the country of the gods).
The first appearance of the word ‘Shintō’ was in contrast to musuhi or Buddhist teaching. In a passage of the Nihon shoki dealing with Emperor Yōmei (d. 587 CE) we read that he ‘believed in the teachings of Buddha (buppō) and revered the way of the kami (shintō). Further on, in the account of Emperor Kōtoku (596-654), we read that the Emperor ‘honoured the teachings of Buddha but disregarded shintō.
Here we see the first recognition of the difference between Shintō and Buddhism. The word buppō (Buddhist teaching) indicates that this is a system of teachings, which one can be said clearly either to believe or not to believe. Shintō, on the other hand, does not have such ‘teachings’, and thus can only be the object of ‘reverence’ or ‘disrespect’. Being the accumulated traditions of the ancestors maintained since ancient times, there can only be two attitudes towards it: respect or disrespect. It is not something in which we can separate truth from falseness so that we can say we believe, or don’t believe it. Here we can clearly see the difference between ‘Buddhism as system of teachings’ and ‘Shintō as accumulated tradition’.
Then, some fifty or more years after its first appearance, when Buddhism, although still new, has had time to become established as a new tradition, we encounter an attitude according to which one either ‘reveres’ or ‘disrespects’ it. Emperor Kōtoku revered ‘Buddhism’ but disregarded ‘Shintō’.
How was his attitude disrespectful to ‘Shintō’? We are told that his disrespect for Shintō was shown by his cutting down trees in the precincts of Ikukunitama Shrine in Settsu Province. His failure properly to care for trees held to be sacred is here recognised as ‘disrespect towards Shintō’.
Based on this difference in awareness as between ‘Buddhism’ and ‘Shintō’, I should like to attempt to show the ‘latent doctrine of Shintō’ in the following way.
Shintō lacks a distinct doctrine, but it is expressed in various forms. I shall try to position Shintō as thus expressed as Shintō’s ‘latent doctrine’ according to the following seven characteristics.
1. Shintō as religion of ‘place’
2. Shintō as religion of ‘way’
3. Shintō as religion of ‘beauty’
4. Shintō as religion of ‘festival’
5. Shintō as religion of ‘technique’
6. Shintō as religion of ‘poetry’
7. Shintō as religion of ‘ecological wisdom’
Shintō is, above all, a ‘poetics of space’ existing as a field, as a place. It exists visibly, and continues to exist, as poetics of the forest (shrine), as geometry of the purified space, as topology of the sacred ground, as memory and document of place. This is the ‘shrine’; this is the ‘guardian forest’.
To be sure, this is not an explicit system of teachings, but it is a practice of a lifestyle – a way of proceeding through life – with a truly stylistic, clear form, a stance on life and living. ‘Shintō’ has lived in ‘shrines’, through ‘shrines’ and together with ‘shrines as places’, as such a traditional culture of a path of life.
In such a ‘place’ or ‘path’, freshness, purity, feeling and atmosphere were valued above all. Many shrine people and Shintoists, when asked what is the most important thing in Shintō, reply ‘cleaning’. Cleaning comes first, second, third and fourth. In this saying that cleaning is the spirit of Shintō, we find a spirit and a sense of adoration and care for the primordial mode of life, the pure origin.
Kakisaka Mikinosuke, Chief Priest of Tenkawa Benzaiten Shrine in the Yoshino Mountains, has called this ‘futomani’. Ordinarily, the word futomani refers to ancient practices of divination, but Chief Priest Kakisaka says that futomani means not fortune-telling, but the natural manifestation of things as they are, acceptance of and dealing with these naturally manifested events and phenomena, and these things are manifested and accepted by ‘cleaning’. Thus, ‘cleaning’ is the foundation and basis of all things.
Shintō, with this ‘latent doctrine’, summed up in the seven points listed above, is a ‘sensory religion’, an ‘artistic religion’. Its sensory characteristic and its artistic characteristic reveal themselves as the mind and body transformation ritual technique called matsuri or ‘festival’.
The essence of matsuri is the renewal and regeneration of life by the performing art of ritual, wazaogi. Its mythical origin is described in writings such as the Kojiki, Nihon shoki and Kogo shūi as the rite performed by the kami in front of the door of the heavenly rock cave. This rite was performed to resurrect the kami Amaterasu, who had hidden herself in the heavenly rock cave (meaning a symbolic death) and to bring about her reappearance. In essence, it expresses a message of death and rebirth.
At this time, the kami Ame-no-Uzume performed a dance holding bamboo grass in her hands, and, entering a trance, exposed her breasts and vulva, causing much laughter among the assembled kami. The female womb is where life is conceived and born, and the breasts nourish and nurture life. By showing these parts of her body, she expressed the birth of life, and the yearning for, celebration of, and joy at the appearance of life was manifested in the laughter of the kami. Incidentally, the ideogram chosen to stand for the word ‘laughter’ in this text is the same character used for ‘flowering’, which enables us to understand their joy at this rebirth.
Matsuri is a celebration of this appearance of life, or miare. This is a reinvigoration, or tamafuri, an activation of life, a technique (waza) of transformation of mind and body of kami and humans to a fullness of life and a state of resonance. Central to this ‘technique’ is performance (wazaogi).
The word wazaogi first appears in the Nihon shoki, where it denotes a spiritual art performance calling forth and activating the soul, as performed by Ame-no-Uzume. It is also the creation of a time and space of eroticism incorporating various sensual and grotesque symbolisms and methods.
This non-routine erotic time and space is a singularity, a ‘poem’, in which mythical time and space come out in a primal opening up into our daily life, and by means of this ‘poem’ the world and life are grasped in a narrative manner and are reincarnated through the circuit of matsuri. In this sense, Shintō is a ‘religion of poetry’, a ‘religion of narrative’.
Thus, Shintō is a religion of tradition, in which life force and wisdom are held in awe and veneration and passed down to be applied in day-to-day life. In contrast to Buddhism, which is a religion of teaching, a religion of enlightenment, Shintō is a religion of tradition, a religion of awe.
As Lafcadio Hearn says, Shintō does seem not to have any explicit philosophy or code of ethics. However, in the ‘manifestation’ of Shintō, through ‘place’, ‘way’, ‘beauty’, ‘festival’, ‘technique’ and ‘poetry’, Shintō’s ‘latent doctrine’ pulsates with a steady pulse. This lifeline of Shintō I call ‘ecological wisdom’. The pulse of ‘ecological wisdom’ alive in the totality of ‘manifestation’ that is Shintō is the kernel of Shintō’s ‘latent doctrine’.
Here, I define this ‘ecological wisdom’ as ‘the wisdom and technique of a system for maintenance of a sustainable and creative balance between the natural and the artificial, developed through keen observation and experience in daily life, based on a profound and humble awe and respect for nature’. Shintō is replete with this profound ‘ecological wisdom’. A concrete expression of this ‘ecological wisdom’ is the regular rebuilding of the shrines at Ise and Izumo and the Kamo Shrine in Kyoto.
4.Differences between, and sharing of work by, Shintō and Buddhism, or kami and Buddha
I have presented an outline of Shintō, defined its characteristics as a religion of the senses, a religion of art, a religion of narrative (poetry) and a religion of ecological wisdom, and positioned it as a religion of tradition and a religion of awe.
Buddhism, however, appeared with characteristics essentially the opposite of these characteristics of Shintō. Firstly, the senses are relativised (the ‘emptiness of the five aggregates’). Art is shunned (song, music and dance which excite sensuality are prohibited or suppressed). One opens one’s eyes to the order of the world (dharma) rather than being intoxicated by stories. By adopting precepts, one consciously severs the chains of ecological wisdom as being samsāra, the cycle of life and death. Denying or relativising traditional systems such as Brahmanism, rather than looking with awe, one practises vijñāna (consciousness) (satori) observing and recognising phenomena as they are (right view).
I have developed the following motto of three differences between kami and Buddha to show the fundamental differences between Shintō and Buddhism:
Fundamental differences between kami and Buddha
1. Kami exists, Buddha comes into being Zaishin / jōbutsu
2. Kami comes, Buddha goes Raishin / ōbutsu
3. Kami stands, Buddha sits Risshin / zabutsu
As I mentioned earlier, ‘Buddha’ is a person who has achieved enlightenment, that is, an enlightened person. ‘Buddha’ is, first and foremost, a person who has seen the suffering of the world and the self as it is and correctly perceived its root cause (a person who has practised ‘right view’ and achieved perfect enlightenment). The truth into which insight is gained at this time is the true nature of things that makes this world exist, impermanence, non-self, dependent origination, emptiness and the like. The aim of Buddhist teaching and Buddhist practice is, by knowing this nature of things, this basis of existence (cognition of truth = satori), to become a wise person who can break free from the reality of suffering which appears through the self – afflictions, pain, doubt – that is, to ‘become Buddha’.
Thus, a person who breaks free from afflictions and doubt and recognises truth is called an enlightened one, or Buddha, and respected as someone who has gained enlightenment, taken as a model of human life, and eventually as an object of devotion.
Buddha is one who has attained a state free from suffering in which afflictions are extinguished (nirvāna, absolute calm, peace of mind), who has crossed from this shore (this world of suffering and doubt) to the other shore (nirvāna). Another name for the Buddha who has broken free from this suffering is ‘king of healing’ and the technique and way he showed is the path of ‘removing suffering and giving peace’.
Thus, ‘Buddha’ is a wise person who consciously shuns the ‘ecological wisdom’ that gives shape to the world of survival, shows the path of escape from the chain of samsāra it forges, and achieves this path himself or herself, and is a very different figure from the powerful presence (nature, animal or plant, hero, ancestor) known as kami.
However, in Japan, a dead person, and by no means necessarily one who has attained enlightenment, is often referred to as ‘hotoke (Buddha)’, and death itself is referred to as ‘odabutsu’, which comes from the name of Buddha. Here, it seems that the scope of meaning of the word ‘hotoke (Buddha)’ has been extended limitlessly so that it even refers to a dead person who has not attained enlightenment. This would seem to be a serious deviation from, even a contradiction of, the original view of Buddhahood. Kami and hotoke are, properly, completely different modes of existence. Nevertheless, in Japan, a unity of opposites has come about. This includes the idea of ‘original enlightenment’ in Tendai Buddhism, according to which all things are already enlightened. Here we see a transformation (collapse or deepening?) of Japanese Buddhism, in which Buddhist practice, which shunned the idea of ‘ecological wisdom’, has been further refined and has come back to the idea of ‘ecological wisdom’.
However, the first fundamental difference between kami and Buddha was ‘kami exists, Buddha comes into being’. Kami is something that exists as a natural phenomenon such as, for example, thunder or water, whereas Buddha is something = someone who has attained enlightenment through practice and thereby become Buddha. Kami ‘exists’, ‘appears’ as the world of being, as phenomena of nature, whereas Buddha is not something that exists as it is, but someone who, through certain practices and experiences has attained the stage of consciousness of an enlightened one.
The second difference is ‘kami comes, Buddha goes’. Kami is a visiting powerful presence that comes like a typhoon, whereas Buddha is a human being who has crossed to the other shore and reached the world of enlightenment free from afflictions, that is, the world of nirvāna. Accordingly, the contrast can be made between kami, which is something that comes (a visiting thing), whereas Buddha is someone who goes to the other shore (one who crosses over).
The third difference is ‘kami stands, Buddha sits’. In Japanese when we count kami we use the counter word hashira (‘pillar’); the famous Onbashira Festival at Suwa Taisha Shrine centres on a sacred pillar called the onbashira. In contrast to this kami, which is a standing thing of power, Buddha is a person who attains liberation by practising zazen, sitting in meditation, and in profound meditation by practising ‘right view’ and ‘right concentration’. We count kami using the counter hashira or ‘pillar’, whereas Buddhas are counted using the word za (seat) or tai (body).
Kami stands, Buddha sits. Here we see the vertical character of kami and the horizontal character of Buddha; the rupturing nature of the ‘shaking’ kami and the interdependent connectedness of the compassionate Buddha; the empowering kami and the expowering Buddha; the grotesque kami and the soft Buddha; the scourging kami and the assuaging Buddha.
Analysed in this way, kami and Buddha are one hundred and eighty degrees apart. These two concepts of the sacred with their completely different principles and orientations have, in Japan, where so many things have been melted down, given birth to and continued to breed a mode of bonding which we call the idea or culture of shinbutsu shūgō, or syncretism of Shintō and Buddhism. Whether we call it the Shintoisation of Buddhism or the Buddhistisation of Shintō, there can be no doubt that a tremendous Japanisation of Buddhism has taken place. The prime example of this Japanisation is the Tendai idea of ‘original enlightenment’ which we see expressed in propositions such as ‘afflictions are enlightenment’, ‘demons and Buddhas are one’ and ‘all things are already enlightened’.
5.Returning to the diversity of Japanese civilisation
Japanese people are frequently said to be ‘tolerant’ in matters of religion. I believe that this ‘tolerance’ stems from the diversity of the Japanese ‘climate’. Broadly speaking, there are two kinds of ‘diversity’ here, natural diversity and cultural diversity.
First, natural diversity. In the land creation myth with which the Kojiki opens, we find the memorable phrase ‘when the land was young it was like floating oil, and drifted like a jellyfish’. Before the Japanese archipelago took shape, it is described as having been like floating ‘oil’, like a drifting ‘jellyfish’.
Living on islands such as these, it is impossible to hold to the unrealistic belief that the earth is solid and unmoving as a rock. These islands are indeed floating and drifting like ‘oil’, or like a ‘jellyfish’.
Under the Pacific Ocean there are massive trenches such as the Japan Trench and the Nankai Trough, while underlying the islands themselves there are major rifts and faults including the Fossa Magna and the Japan Median Tectonic Line. The Japan Trench at its deepest point is 8,020 metres deep, nearly the same as the height of Mt. Everest, which is 8,848 metres, and is formed by the sinking of the Pacific Plate under the North American Plate. The Nankai Trough, on the other hand, is formed by the sinking of the Philippine Sea Plate under the Eurasian Plate. Meanwhile, the great north-south rift known as the Fossa Magna is at the border between the North American and Eurasian Plates. At the interface of these plates are active volcanoes including Yakeyama, Myōkōsan, Shiranesan, Asamayama, Yatsugatake, Fujisan and the Hakone Mountains, presenting a spectacular landscape.
In 1968, the scholar of Japanese literature Masuda Katsumi (1923-2010) argued in the book Kazan rettō no shisō [Intellectual culture of the volcanic archipelago] (Chikuma Shobō) that the archetype of ‘the kami that could only be born in Japan, the true native kami of these islands’ was the kami Ōnamochi. From records that ‘there was a kami in the sea off the coast of Ōsumi Province, who created an island. The name of this kami was Ōnamochi,’ Masuda infers that ‘Ōnamochi was the name given to the kami of a seabed eruption, and concludes that this name means ‘a kami who has a large hole (ō-ana-mochi)’ and that this is ‘the deification of the volcano itself with its large crater’.
Japan is a volcanic archipelago. It is also an earthquake archipelago, a typhoon archipelago and a heavy snow archipelago. In summer it is lashed by wind and rain from typhoons; in winter by wind and snow. Summers are hot, winters cold. There are few countries with similarly extreme weather cycles.
Japan is the only country sitting on a tectonic crossroads with four overlapping plates. What is more, these islands are surrounded by four ocean currents: two warm currents, the Kuroshio or Japan Current and the Tsushima Current, and two cold currents, the Oyashio or Kuril Current and the Liman Current, collide with each other in the waters of the Pacific Ocean and the Sea of Japan. This results in the complex and varied marine fauna at the confluence of these ocean currents, which makes excellent fishing waters. Then there are the two major forest zones of the laurel forests of western and lowland Japan and the oak-beech forests of eastern and upland Japan. Thus, the geology and physical geography of the Japanese islands present a crucible of complexity and diversity rare in the world.
Then, overlying this is a historical-geographical complexity and diversity. From three directions, north, west and south, peninsular, continental and island elements from the Korean peninsula, continental China and the islands of Southeast Asia have flowed in and combined, giving birth on the Japanese islands to a truly hybrid culture and civilisation.
The diverse, multi-layered, pluralistic and varied nature of the Japanese archipelago in all its aspects, tectonics, weather, oceanography, fauna and flora, environment, ecosystem, culture and civilisation, served as the ‘climatic’ condition, or womb, for the birth in these islands of a polytheism we call ‘yahoyorozu no kami’, and in the records Kojiki, Nihon shoki and Fudoki these kami go on a veritable rampage. A wild, frantic, breathless tumult it was.
This state is described at the beginning of Part Two of the Age of the Gods in the Nihon shoki: ‘[Taka-mi-musubi] desired to establish his august grandchild Ama-tsu-hiko-ho-ho-ninigi-no-Mikoto as the Lord of the Central Land of Reed-Plains. But in that Land there were numerous Deities which shone with a lustre like that of fireflies, and evil Deities which buzzed like flies. There were also trees and herbs all of which could speak. Therefore Taka-mi-musubi no Mikoto assembled all the eighty Gods, and inquired of them, saying: “I desire to have the evil Gods of the Central Land of Reed-Plains expelled and subdued. Whom is it meet that we should send for this purpose?”’ (W.G. Aston, trans., Nihongi: chronicles of Japan from the earliest times to A.D. 697)
In other words, there were many kami shining like fireflies and evil kami making clamorous noises, and even the trees and grasses were talking. This is a mythical expression of the volatile nature of the environment with its many volcanoes, earthquakes and typhoons. These nature deities conducted themselves in a violent way. Unless they were assuaged, development of the land, rice cultivation and national unity could not proceed. How can this land, with its complex and fragmented multiplicity of kami, be brought together? This can be said to be the main theme of Japanese culture and thought.
Originally, the word kami was a coverall word used with a sense of awe, respect and praise for the dynamic movement of these various natural events and the wildness of their diversity, to offer an analogy, it was something like a computer ‘folder’. A folder is an assemblage or a category in which we can enclose a multiplicity of related items, or ‘files’, by putting into it various items of information, formats and conditions.
The ‘kami folder’ was a ‘folder’ in which are kept together certain sacred feelings, knowledge, powers and phenomena embraced by people living on the Japanese islands.
For example, there are a number of words expressing divine power, divinity, spirituality or spiritual power in what we might call the ‘chi file’, such as ikazuchi (thunder spirit), kagutsuchi (fire spirit), nozuchi (field spirit), kukunochi (tree spirit), mizuchi (water spirit). This ‘chi’ is the origin of the makurakotoba or poetic epithet for kami found in the Man’yōshū anthology, ‘chihayaburu’. Thunder, fire, trees and water are all natural events and natural things. They are manifestations of the generative power musuhi creating and moving the world by the dynamic of wild force. In the Nihon shoki this musuhi is written as ‘birth-giving spirit’.
Words with this suffix hi, what we might call the ‘hi file’, include musuhi (birth-giving spirit), naohi (good spirit), magatsuhi (evil spirit). This group of divine powers or divinities expresses certain functionalities or workings.
Besides these, there are the ‘mi file’ including yamatsumi (mountain spirit) and wadatsumi (sea spirit), which indicates a comparatively wide natural realm, and many other words and concepts expressing divine power, divinity, spiritual power or spirituality, of which we can mention mono, nushi, tama, oni and mikoto.
While these ‘file’ groups expressing the divine powers, divinities, spiritual powers and spiritualities of chi, mi, hi, mono, nushi, tama, oni and mikoto were forming clusters, a sense for recognising the generation and manifestation of kami in all these natural phenomena near and far was incorporated and enveloped in the overall ‘folder’ of kami.
It is in these natural geographical, historical geographical and cultural conditions that the religious spirit of the Japanese islands formed. In other words, the bedrock of ‘Shintō’ is a gathering point of converging tectonic plates and converging cultures, a symphony of Eurasian/Circum-Pacific ritual culture, and this ‘Shintō’ which developed on the Japanese islands is a three-dimensional crossroads of the nature and culture of these islands.
In this ‘climate’ the native religion Shintō and the new arrival Buddhism syncretised to produce a peculiar syncretic culture. This Shintō-Buddhist syncretic culture has been a basso continuo sounding through Japanese culture to the present day.
I believe that, long before this syncretism of kami and Buddha was worked out, various ‘kami’ came together at this meeting point of tectonic plates, this crossroads of major oceanic currents, and developed a culture of symphonic ‘syncretism of kami and kami’, and it was on this ground that, much later, in the 6th century CE, Buddhism was brought first from the Korean peninsula and soon afterwards from continental China, and mingled with the local kami to bring about a ‘syncretism of kami and Buddha’.
Thus, I believe that ‘syncretism of kami and Buddha’ is one branch of ‘syncretism of kami and kami’ and it is the ‘diversity’ that has its basis in this convergence/syncretism that has given birth to the ‘tolerance’ which is an expression of the ‘Japanese religious spirit’. It will be necessary, by floating like a soft jellyfish, to survive the upheavals of the 21st century, with this ‘diversity of Japanese culture’ as our national characteristic, and hardily to endure. This is the conclusion of my theory of Shintō.
神道と日本文明(鎌田東二)
文明の発達には物質的基盤として食料などの生産力の増大とそれを運搬する交通手段や交通網とそれを支える技術革新と共有が必要である。また、それらの大規模なシステムを円滑に運営して行くための法律や記録や文字が必要となる。だが、それ以上に、それらを長期にわたって安定的に維持していくためには、そこで生活する人々の精神的安定を図るもたらす基軸としての宗教や世界観が必要となる。したがって、日本の文明の形態と歴史とその特色を考えていく際には、そこにおける宗教が何であったかを検証してみることには大きな意味がある。文明的条件とも言える、強大な権力の確立と階級分化、法体系の整備、巨大建造物の建設、生産力の向上と交通網の発達、都市の成立、文字の使用と文書の刊行、宗教制度の整備などが、一つのシステムとして日本列島に整ってきたのは紀元後7~8世紀の律令体制の確立期である。具体的には、天武天皇(在位673‐686年)、持統天皇(在位690-697年)、文武天皇(在位697-707年)、元明天皇(在位707-715年)、元正天皇(在位715-724年)、聖武天皇(在位724-749年)の治世が日本文明の確立期と言える。
第一章 日本文明の始まり
文明の発達には物質的基盤として食料などの生産力の増大とそれを運搬する交通手段や交通網とそれを支える技術革新と共有が必要である。また、それらの大規模なシステムを円滑に運営して行くための法律や記録や文字が必要となる。だが、それ以上に、それらを長期にわたって安定的に維持していくためには、そこで生活する人々の精神的安定を図るもたらす基軸としての宗教や世界観が必要となる。
したがって、日本の文明の形態と歴史とその特色を考えていく際には、そこにおける宗教が何であったかを検証してみることには大きな意味がある。
文明的条件とも言える、強大な権力の確立と階級分化、法体系の整備、巨大建造物の建設、生産力の向上と交通網の発達、都市の成立、文字の使用と文書の刊行、宗教制度の整備などが、一つのシステムとして日本列島に整ってきたのは紀元後7~8世紀の律令体制の確立期である。具体的には、天武天皇(在位673‐686年)、持統天皇(在位690-697年)、文武天皇(在位697-707年)、元明天皇(在位707-715年)、元正天皇(在位715-724年)、聖武天皇(在位724-749年)の治世が日本文明の確立期と言える。
例えば、天武天皇の治世に伊勢神宮が整備され、持統天皇の治世の始まった690年10月に第1回目の式年遷宮が始まったとされる。以来1300年余、2013年10月には第62回目の式年遷宮が行なわれた。このような巨大な祭祀システムが長期にわたって機能し継続されること自体が日本文明の確立とその連続性の証拠の一つとなる。
また、持統天皇の治世の690年に建設が開始され、4年後の694年に飛鳥浄御原宮から遷都した藤原京の成立も、日本で初めて条坊制が取り入れられた宮都の建設であり、特筆すべき出来事であった。そして、元明天皇の治世の710年に平城京に遷都し、712年には『古事記』が編纂され、その8年後の720年には日本国家の公式の歴史書である『日本書紀』が編纂されている。とすれば、690年から720年に至る30年の間に日本文明システムの根幹が確立したと言っても間違いではないだろう。
その後、聖武天皇の治世の743年に東大寺の大仏造立の詔が出され、その10年後の752年に大仏開眼会が執り行われた。これもまた日本文明の中に国家仏教が強力かつ明確に組み込まれて国内外に顕示された証拠である。とすれば、第1回目の式年遷宮(国家的規模の神道儀礼)が行なわれた690年から東大寺大仏の開眼会(国家的規模の仏教儀礼)が行なわれた752年に至る約60年余が神仏共存補完体制を含む日本文明の確立期と位置づけることができる。以来、約1300年、少なくとも日本文明は神社や寺院や天皇制という点で強い連続性を保持してきた。この長期にわたる連続性は他の文明には見られない日本的特質と言えるものである。
第二章 日本文明の多様性の地質学的基盤としての日本列島のプレート多様性
その日本文明の根本特徴とはどのようなものか? これをわたしはさまざまなレベルでの「多様性」に見る。
その多様性は、まず第一に4枚のプレートの集合という地質学的にも類例を見ない日本列島の「プレート多様性」として現われ、第二にその上に展開する動植物相の「生物多様性」として現われ、第三に東海の孤立した列島に流れ込んでいく「文化多様性」として現われ、第四にその文化の中核をなす宗教的な観念の「神々の多様性」として現われた。これらを総称して「日本文明の多様性」と言うことができる。
8世紀初頭にまとめられた『古事記』においては、その「神々の多様性」を「八百万の神々」と呼んだ。もちろん、8世紀には、神社として具体化される神祇信仰や神道ばかりでなく、寺院や僧侶として具現される仏教や儒教や道教も日本文明を構成する宗教要素として取り入れられている。そしてすでに、「宗教多様性」の一つの現われとして、「神仏習合」が始まっている(1)。このような「多様性」を「国体(国柄・国の特性)」とするのが「日本」なのである。
日本は四方を海に囲まれた島嶼列島である。今から約12000年ほど前に現在のような日本列島ができあがった。氷河期が終わり、北極圏の氷床が溶け出し、水位が上がると、それまでユーラシア大陸とつながっていた半島は、完全に四方を海に囲まれた島嶼となり、列島となったのである。
そして、相前後して、世界でもっとも古い土器文化とされる縄文時代が始まり、独自の日本列島の風土と文化の形成が始まった。その日本の風土の特徴は、まず第一に、先に述べたように、四方を海に囲まれた島々であるということ。つまり、島国という風土である。第二に、その島々は火山列島で、4つのプレートの集合地であった。ユーラシアプレートと北米プレートとフィリッピン海プレートの4つのプレートがぶつかる地質学的にも大変珍しい地帯にある日本列島は、そのために火山の噴火活動が活発で、地震も多く、列島自体が揺らぎの中にある。『古事記』には、そのような振動する日本列島の姿を「くらげなす漂える国」と呼んでいる。第三に、火山活動やプレートのぶつかり合いによる褶曲運動のため、急峻な山々が多く、山岳や森林が国土の約70%を占め、それゆえに清流の流れる河川や沢や沼地が多く、そのことがやがて数多くの水の信仰と独自の水の文化を生み出していった。
このように、日本は海の水と川の水の両方の豊富な水に取り囲まれた水の列島だった。そのために、後に大陸から農耕文明がもたらされた時、日本の名称を「豊葦原の瑞穂 (水穂)の国」(豊かな葦の生い茂る水と稲穂に恵まれた国という意味)と称えて呼ぶようになったのである。ちなみに、『古事記』には、日本の古い呼び名として、「大八島国」(大きな八つの島のある国)と「豊葦原の瑞穂の国」と「くらげなす漂える国」という3つの呼び名が出てくる。それに対して、その少しあとにまとめられた日本最初の公式文書であった『日本書紀』は、呼び名を「日の本」としての「日本」という名で統一している。
こうして、8世紀には「日の本・日本」と呼ばれるようになりますが、その太陽の国「日の本」は古く火山の国「火の国」であった。そのことは、日本の西南部の島・九州の国々を古くは「ヒの国」と呼んだことにもその痕跡をとどめている。
こうしてみると、日本は水の国であり、火の国また日の国であったといえる。その島々や国々の呼び方の中に日本の風土的特質があますところなく表現されている。江戸時代の神道思想の一つ表現として、「火と水」と書いて「カミ」(神)と読ませるようになるが、火と水の自然の生成力の中に神聖な力の顕現を見たことは日本神道の重要な伝統となっている。
第四に、日本の森林相には大きく北方系のブナ・ナラ林帯と南方系の照葉樹林帯の2種があるが、どちらも保水能力に優れた森林で、その豊かな養分を含んだ水と土の成分が海の幸、山の幸、川の幸、野の幸をもたらした。つまり、豊富な植生と食糧を産出する生態系をもたらした。そのような自然産出力を『古事記』は「むすひ」(「産巣日」、『日本書紀』では「産霊」と表記)と呼んでいる。
以上の4つの特質を日本の風土的特質として挙げることができる。この自然風土を離れて日本人の信仰と宇宙観は生れることはなかったし、その信仰と宇宙観の表現としての神道も生れることはなかったのである。
第三章 神道とは何か?
それでは次に、「神道」とは何か、を見てみよう。
神道の起源をどこに見るかについて、西田長男、梅原猛、太田龍、小林達雄、鎌田東二は神道の起源を縄文に見る。例えば、縄文考古学者の小林達雄は、「縄文的伝統の心が弥生・古墳などを経て、古代まで連綿と継承されている事実」「神社成立はそれほどに根深い伝統に由来するものだった」(鎌田東二編『日本の聖地文化』創元社、2012年)と述べている。それに対して、神道系大学の教授や学長を務めた安津素彦や上田賢治らは神道における農耕儀礼や皇室儀礼の重要性を踏まえて神道の起源を弥生時代に見定めている。
そのどちらにもそれなりの言い分があるので、どちらが正しいと言い切ることはできないが、しかし、間違いなく、縄文時代の「カミ」観念が8世紀に『古事記』や『日本書紀』などにまとめられていく「八百万の神々」の中に流れ込み、溶け込んでいると考えられる。
それでは、その神道の確立期はいつ頃かと言えば、冒頭の第一章で述べたように7~8世紀の律令体制期確立期であろう。とりわけ、天武天皇と持統天皇の治世が画期をなす時期で、そのグランドデザインをしたのは、上山俊平や梅原猛が指摘したように藤原不比等であっただろう(上山俊平『天皇制の深層』朝日新聞社、1985年、梅原猛『海人と天皇』朝日新聞社、1991年など参照)。
「神道」とは何かを明確に語ることは容易くはない。その理由の第一は、神道には明確な教え・教義というものがないからである。そのために、「神道は教義なき宗教である」という言い方がなされる時がある。それはあながち間違いではないが、だからと言って、何もないわけではない。神社はあるし、祭りもある。『古事記』や『日本書紀』や『古語拾遺』や『先代旧事本紀』などの神話や家伝を記した古典もある。明確な教義こそないが、そこには何らかの「潜在教義」がある。
それに対して、仏教には明確な教義がある。例えば、「三法印(諸行無常・諸法無我・涅槃寂静)」、「四諦(苦諦・集諦・滅諦・道諦)」、「八正道(正見・正思・正語・正業・正命・正精進・正念・正定)、「十二縁起(無明・行・識・名色・六入・触・受・愛・取・有・生・老死)」などは、仏教の要諦とも根本教義といえるものである。これら釈迦仏教や初期仏教の教説を基盤として、大乗仏教の中観派や唯識派の存在論や認識論が生まれ、さらには密教の真言や曼荼羅の思想と実践(修法)体系も編み出されてくる。そのような意味では、仏教とは、教義の飽くなきイノベーションに多大なる精力を注入してきた思索と実践の総体であるということができる。
ラフカディオ・ハーンは神道が実にしぶとい生命力を以て日本文化の芯として生き続けていることを次のような逆説的な言葉で讃美した。
「仏教には万巻に及ぶ教理と、深遠な哲学と、海のように広大な文学がある。神道には哲学はない。体系的な倫理も、抽象的な教理もない。しかし、そのまさしく『ない』ことによって、西洋の宗教思想の侵略に対抗できた。東洋のいかなる信仰もなし得なかったことである」(『神々の国の首都』小泉八雲著、平川祐弘編、講談社学術文庫)。
文献上、「神道」という語は、「仏法」との対比を通して、『日本書紀』用明天皇(?-587年)の条に「信仏法、尊神道」と初出するのが最初で、次に、同じ『日本書紀』孝徳天皇(596-654)紀に「尊仏法、軽神道」と出てくるのが二例目である。
ここに、最初の神道と仏教(正確には「仏法」)との差異の認識が出ている。つまり、「仏法」には「法」という教えの体系であるから、それを信じるか信じないか、信不信をはっきりと表わすことができる。しかし、「神道」はそのような「法」を持たず、教えの体系ではないから信不信ではなく、「尊」か「軽(不敬)」の対象でしかない。つまりそれは、古来維持されてきた先祖伝来の伝承の集積だから、それを大事にするか大事にしないか、敬うか敬わないかという二つの態度しかない。信じるとか信じないとかというように、はっきりとその対象の真偽性を事分けることはできないという構えである。ここで、「教えの体系としての仏法(仏教)」と、「伝承の集積としての神道」との違いがはっきりと出ている。
それから50年以上が経って「仏法」がある程度定着してくると、今度はその「仏法」も新しいとはいえ一つの新伝統となるから「尊(敬)」するかしないか(「軽(不敬)」)という態度で接することができる。孝徳天皇は「仏法」を尊び、「神道」を軽んじた。
それでは、どのような態度が「神道」を軽んじることであったかというと、それは摂津国の生国魂社の境内の樹を伐ることが「軽神道」に当たるというのであった。神木とされているような樹を大事にしない態度、それが「軽神道」のしわざであるという認識がここにはあった。
このような「仏法」と「神道」に対する認識の違いを踏まえて、わたしは「表現(あらわれ)としての神道」の「潜在教義」を次の七つの特性として位置づけてみたい。
① 「場」の宗教としての神道
② 「道」の宗教としての神道
③ 「美」の宗教としての神道
④ 「祭」の宗教としての神道
⑤ 「技」の宗教としての神道
⑥ 「詩」の宗教としての神道
⑦ 「生態智」としての神道
「神道」は、まず何よりも、「場」として、「場所」としてある、「空間の詩学」として、森(杜)の詩学として、斎庭の幾何学として、聖地のトポロジーとして、場所の記憶(メモリー)と記録(ドキュメント)として、存在し続けてきた。それが「鎮守の森」としての「神社」であった。
それは確かに、明示的な教えの体系ではないが、実に様式的な、明確な形を持った「道=生の歩み方(ライフスタイル)」の生活実践であり、いのちと暮らしのかまえであった。そのようないのちの道の伝承文化として、「神社」の中に、「神社」を通して、「神社という場」とともに「神道」は生きてきた。
そのような「場」や「道」にあっては、何よりも清々しさ、清浄感や、もののあはれや、気配の感覚が大切にされた。多くの神社人や神道家は、神道で一番大事なのは「掃除」だという。一にも掃除、二にも掃除、三にも四にも掃除。掃除こそが神道の精神であるという表現には、そこに生命の原初形態、純粋始源を讃美しいつくしむ心と感覚がある。
奥吉野山中に鎮座する天河大辨財天社の柿坂神酒之祐宮司は、それを「ふとまに」と呼んだ。一般には「太占(ふとまに)」とは、古代の卜占のことを指す。しかし柿坂宮司はそのような「うらない」のような吉凶判断ではなく、「ふと」そのま「まに」、ものごとが立ち現われてくる、その「ふと・そのまま・に」立ち現われてくる出来事や現象をそのまま受け取って対処していくこと、それが「ふとまに」であり、それは「掃除」をすることによって、立ち現われ、受け取られると主張する。だから神道は、「禊祓」にも通底する「掃除」を基盤として成り立っている。
神道とは、以上の7つの「潜在教義」を持った「感覚宗教」であり、「芸術・芸能宗教」である。その感覚性や芸術・芸能性が、「祭り」という身心変容儀礼のワザとなっていく。
「祭り」の主旨は、祭祀という「ワザヲギ」による生命力の更新・復活にある。その神話的起源が、天の岩戸の前で行われた神々による神事として、『古事記』や『日本書紀』や『古語拾遺』の中に語られている。その神事は、天の岩戸に隠れた(象徴的な死を意味する)天照大御神を甦らせ、再顕現させるために行なわれた。つまるところ、「死と再生(復活)」がメッセージとして表現されている。
この時、アメノウズメノミコトが手に笹を持って踊りを踊るのであるが、その際、「神懸り」となり、胸乳と女陰(ホト)を露わにして神々が大いに「咲(わら)ふ」。女陰はいのちを宿し、産み出す器官であり、胸乳はいのちに栄養を与え、育む身体部位である。そのような身体部位を露わにすることによって、いのちの出生を表現し、そのいのちの現われ、すなわち「御在(みあ)れ」を待ち望み、寿ぎ、喜ぶ心が神々の「咲(わら)ふ」行為となって現われる。この「わらい」に、あえて漢字の「咲」の字を宛てていることからも、その再生への歓喜を読み取ることができるだろう。
「祭り」とは、このような「いのちの出現=みあれ」に対する祝宴である。それは、生命力を賦活し、活性化させる「鎮魂(たまふり)」であり、神々や人々の身心を生命的横溢と共鳴状態に変容させる「技(わざ)」である。その「技」の中核をなすのが、「ワザヲギ」である。
「ワザヲギ」とは、アメノウズメノミコトが行なったたましいを呼び出し、付着させたり、活性化させたりするスピリチュアル・アート・パフォーマンスを指す言葉として『日本書紀』に初出する。それはまた、さまざまな妖艶・怪異なシンボリズムと手法も組み込んだエロティシズムの時間と空間の創造でもある。
この非日常的なエロス的な時空は、生活の中に神話的な時間と空間が開基してくる特異点であり、「詩」であるが、そうした「詩」によって、世界といのちを物語的にとらえ、祭りの回路を通して再受肉する。神道は、そのような意味での「詩の宗教」であり、「物語宗教」である。
このようにして、いのちのちからと知恵を畏怖・畏敬し伝承し、暮らしの中に生かす伝え型の宗教が神道である。教え型の宗教であり、悟りの宗教としての仏教に対して、神道は伝え型の宗教であり、畏怖の宗教であると対比できる。
ラフカディオ・ハーンが言ったように、確かに神道には明示的な哲学も倫理もないように見える。だが、その神道の「あらわれ」の中に、「場」や「道」や「美」や「祭」や「技」や「詩」を通して、神道の「潜在教義」が脈々と脈打っている。そのような神道の生命線を、わたしは「生態智」と呼んでいる。神道という「あらわれ」の総体の中に息づく「生態智」の脈動、それこそが神道の「潜在教義」の核であろう。
この「生態智」を「自然に対する深く慎ましい畏怖・畏敬の念に基づく、暮らしの中での鋭敏な観察と経験によって練り上げられた、自然と人工との持続可能な創造的バランス維持システムの知恵と技法」と定義しておく。神道には、そのような深層的な「生態智」が詰まっている。伊勢神宮や出雲大社や賀茂神社などで行われる「式年遷宮」はそうした「生態智」の具体的な表現でもある。
第四章 神と仏、あるいは神道と仏教の差異と共働
第三章で、神道の特性を、感覚宗教、芸術宗教、物語宗教(詩的宗教)、生態智宗教などとし、伝え型の伝承宗教とも、畏怖の宗教と位置づけた。それに対して、仏教は、本来、神道的特性とは全く異なる特性を持って登場してきた。
例えば、仏教は感覚を相対化する(五蘊皆空)。芸術を遠ざける(官能を刺激する歌舞音曲の禁止や抑制)。物語に酔い痴れるのではなく、世界の理法(ダルマ)に目覚める。あえて、戒律を設けることによって、輪廻転生という生態智的な連鎖を断ち切る。バラモン教のような伝承の体系を否定ないし相対化し、畏怖するまなざしから、ありのままにものごとを見つめ、認識(正見)しようとする識(覚・悟)の実践が仏教なのである。
こうした神道と仏教の原理的な差異を、わたしは「神と仏の三異」と見る。
神仏三異
① 神は在るモノ/仏は成る者 在神/成仏
② 神は来るモノ/仏は往く者 来神/往仏
③ 神は立つモノ/仏は座る者 立神/座仏
先に述べたように、「仏」とは悟りを開いた人、すなわち覚者を意味する。「仏」は、先ず何よりも、世界と自己の苦の姿のありのままの姿とその拠って来る由縁を正しく見抜いた人(「正見」した人、「無上正等覚」)である。その時に洞察された真理が、無常、無我、縁起、無自性、空といった、この世界を成り立たせている真正のありようである。そのありよう・成り立ちを知ること(真理認識=悟り)によって、自己を通して現われ出る苦の現実、すなわち、煩悩、苦しみ、迷いを切断し、解脱していく叡知的存在(智慧ある人間)と成ること、すなわち、「成仏」を目指すのが「仏教」であり「仏道」修行(実践)である。
このようにして、煩悩と迷いを脱した真理認識者は解脱者とか覚者とか仏陀と呼ばれ、悟りを得た人としてリスペクトされ、人生の模範とも、やがては、「帰依」の対象ともなる。
ブッダは、煩悩の消滅した苦しみのない状態(涅槃寂静・絶対平静・安心)に達し、苦と迷いの世界である此岸(俗世間)から彼岸(涅槃)に渡った成就者である。この苦からの解脱者であるブッダのまたの名を「医王」と呼び、その指し示すワザと道は、「抜苦与楽(ばっくよらく)」の道である。
「ブッダ(仏陀)」は生存世界を形作る「生態智」からあえて距離を取り、それが生み出す輪廻の鎖から抜け出す道を指し示し、自らその道を成就した知恵ある人間であり、「(ちはやぶる)カミ」と呼ばれる力ある諸存在(自然・動植物・英雄・先祖など)とは、全く異なる存在である。
ところが、日本では、決して悟りを開いたわけではない死者のことも「ホトケ(仏)」と言ったり、死ぬこと自体を「お陀仏」と言ったりもする。そこでは、「ホトケ(仏)」の指示領域が、悟りを得たわけではない死者をも指すようにまで無際限に拡張されている。これは、本来の仏陀観からすれば、相当な逸脱、逆転とも言えるほどの転倒である。本来、「カミ」と「ホトケ」は全く異なる存在形態だからだ。それが日本で「反対物の一致」を引き起こした。「草木国土悉皆成仏」などの天台本覚思想を含めて。これは、「生態智」思想からあえて離れたブッダの実践がさらなる洗練された「生態智」思想に回帰した日本仏教の変容した姿である。
さて、「神」と「仏」の原理的差異とは、まず第一に、「神は在るモノ/仏は成る者」という差異である。神は、イカヅチ(火雷)・ミヅチ(水霊)などさまざまな自然現象として「在るモノ」だが、仏は修行して悟りを開くことによって「成仏」する「成る者」=人間である。神は存在世界として、自然現象として「在る」「現われる=御在れする」のに対して、仏とはそのままの存在ではなくある修行や体験を通して覚者という意識段階(識位)に到達した「成る者」である。
第二に、「神は来るモノ/仏は往く者」という差異。神はどこからか「マレビト」や台風のように来訪する威力ある諸存在であるのに対して、仏は彼岸に渡り煩悩なき悟りの世界すなわち涅槃寂静の世界に到達した人間である。したがって、神は来るモノ(来訪するモノ)、仏は彼岸に往く者(渡る者)とその違いの対照性を示すことができよう。
第三に、「神は立つモノ/仏は座る者」という差異。神は「一柱、二柱…」などと「柱」という数詞で呼ばれ、諏訪大社の御柱祭における「御柱」のように立ち現れる威力あるモノであるのに対して、仏は坐り、座禅をして、深い瞑想の中で「正見・正定」し、解脱する者である。神は柱を数詞とするのに対して、仏は座や体を数詞とする。
神は立ち、仏は座る。神の垂直性と仏の水平性が現われている。ちはやぶる神の断裂性に対して、慈悲深き仏の縁起的関係性。注力(エンパワメント)する神と脱力(エクスパワメント)する仏。神の異形性と仏の柔和性。祟る神と鎮める仏。
このように分析してみると、神と仏は一八〇度異なる存在である。そのまったく異なる原理や志向性を持つ二つの神聖概念が、いろいろな物事をメルトダウンしてきた日本列島の中で、「神仏習合」思想ないし文化という接合形態が生まれ、増殖しつづけた。これを「仏教の神道化」とも「神道の仏教化」とも言うことができる。いずれにしても、はなはだしい仏教の「日本化」が起こった。「煩悩即菩提」「魔仏一如」「草木国土悉皆成仏」などと命題化していった「天台本学思想」などはその際たる「日本化」の表現である。
第五章 ふたたび日本文明の多様性
一般に、日本人は宗教に対して「寛容」であると言われる。この「寛容」さは日本の「風土」の「多様性」に由来する。その「多様性」を自然多様性と文化多様性に二大別することもできる。
第一の自然多様性の根幹は、先に述べたように4枚のプレート複合であった。『古事記』冒頭の国生み神話でそれは「国稚く浮きし脂の如くして、海月なす漂へる時」と表現されている。未だ日本列島が形を成していない時の様子を「あぶら」が浮き、「くらげ」がフワフワと漂っているような状態であると形容しているのである。
その「くらげ」のような日本列島は、それゆえ、太平洋沖には日本海溝や南海トラフなどの深く巨大な海溝があり、列島下にはフォッサマグナや中央構造線という大地溝帯や大断層がある。日本海溝の最深部は8848メートルのエベレスト山にも相当する8020メートルで、太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込んでできたものである。それに対して、南海トラフはフィリッピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでできた。また、南北の巨大な地溝帯のフォッサマグナは北米プレートとユーラシアプレートの境界にあって、その境界面上に焼山、妙高山、白根山、浅間山、八ヶ岳、富士山、箱根山などの活火山が並んでいる。そのさまは実に壮観である。
益田勝実は『火山列島の思想』(筑摩書房、1968年)の中で、「この日本でしか生れなかった神々、この列島生えぬきの神々」の典型が「オオナモチ(大穴持)」であると主張している。益田は、「大隈の国の海中に神ありて、島を造る。その名を大穴持の神と曰ふ。ここに至りて官社となす」とかの記録から、「海底噴火の神がオオナモチと呼ばれた」と推測し、それは「大きな穴を持つ神」であり、「噴火口を擁する火山そのものの姿の神格化以外ではない」と結論づけたのである。
日本は火山列島であり、地震列島であり、台風列島であり、豪雪列島である。夏には台風による大雨と大風が、冬には大雪と大風が吹き荒ぶ。夏は暑く、冬は寒い。これほど激しく極から極へと変動する気象周期を持っている国も少ない。
このように、一国に四枚ものプレートが重なり合っているプレートの十字路のようなプレート密集地帯は日本列島だけである。加えて、その列島の周囲を二種の暖流すなわち黒潮(日本海流)と対馬海流と、二種の寒流すなわち親潮(千島海流)とリマン海流という、合計四種海流が流れ込み、太平洋と日本海の沖合でぶつかりあっている。そのためにその合流地点には複雑多様な魚介類が集結し、最良の漁場となっている。さらには西日本や低地日本の照葉樹林帯と東日本や高地日本のブナ・ナラ林帯という大きく二種の森林相がある。このように、日本列島の地質学的自然地理学的特質とは、地球上でも稀なる複雑性と多様性のるつぼなのである。
その上に、さらに歴史地理学的な複雑多様が上書きされる。すなわち、北方、西方、南方の三方から、半島的要素(朝鮮半島から)、大陸的要素(中国大陸から)、南島的要素(東南アジアの島嶼から)が入り込んできて、日本列島上で実にハイブリッドな文化・文明習合が生まれることになった。
このように、日本列島がプレート、気候、海流、動植物相、環境、生態系、文化・文明のすべての局面で多様・多層・多元・多種であることが「風土」的条件とも胞衣ともなって、この日本列島に「八百万の神々」と呼ばれるような多神教が発生することになり、それが『古事記』や『日本書紀』や『風土記』の中でさまざまに形容されている。
例えば、『日本書紀』「神代下」の冒頭には、「皇孫天津彦彦火瓊瓊杵尊を立てて、葦原中国の主とせむと欲す。然も彼の地に、多に螢火の光く神、及び蠅声す邪しき神有り。復草木咸に能く言語有り。故、高皇産霊尊、八十諸神を召し集へて、問ひて曰はく、「吾、葦原中国の邪しき鬼を撥ひ平けしむと欲ふ。当に誰を遣さば宜けむ」とある。
つまり、蛍の火のように光り輝く神や騒々しい音響を発する悪い神々がたくさんいて、草木も言葉を話していたと言うのだ。これは火山や地震や台風が多い、自然環境が実に変化に富んだ大変動帯であったことの神話的表現であろう。その自然神は荒ぶる振る舞いをしていた。それを鎮めなければ、国土開発も、米作も、国家統一もできない。そのような、複雑でバラバラで統一性のない多種多神の風土をどのように統合することができるのか、それが日本の文化・文明と思想の主題になっている。
本来、「カミ(神)」という語は、そのような多様な自然事象の振る舞いのダイナミックは運動と多様性の凄みを畏怖畏敬と讃嘆の思いを込めて使用した一種の「風呂敷言語」、喩えて言えば、パソコンの「フォルダ」のようなものであった。「フォルダ」とは、さまざまな情報や形態や状況をとりあえずその中に入れ込むことで関連するものをすべて包み込む、複数の「ファイル」を包み込む集合ないしカテゴリーである。
「カミ・フォルダ」とは、日本列島に住む人々が抱いてきたある特定の聖なる感情や情報や力や現象を取り込み一まとめに総括した「フォルダ」であった。
例えば、神威や神格や霊性・霊威を表わす言葉に、イカヅチ(雷神)、カグツチ(火神)、ノヅチ(野神)、ククノチ(木神)、ミズチ(水神)という「チ系ファイル」がある。この「ち」が、「ちはやぶる神」という『万葉集』の枕詞の元になっている語源である。雷も火も木も水もすべて自然現象であり自然物である。それが荒々しい力の力動で世界を作り上げ動かす「むすひ」(『日本書紀』では「産霊」と表記)の生成力の発現である。
その「ひ」を語尾に持つ「ヒ系ファイル」が、ムスヒ(産霊)、ナオヒ(直霊)、マガツヒ(禍霊)などで、これらは一定の機能性(はたらき)を示す神威・神格群である。
加えて、ヤマツミ(山神)、ワダツミ(海神)などの比較的大きな単位の自然領域を示す「ミ系ファイル」や、他にも、モノ(物)、ヌシ(主)、タマ(魂)、オニ(鬼)、ミコト(命、尊)など、神威・神格・霊威・霊格を表わす実に多くの言葉と観念があった。
こうして、チ系、ミ系、ヒ系、モノ・ヌシ・タマ・オニ・ミコト系などの神威・神格・神性、霊威・霊格・霊性を表わす「ファイル」群が群生しつつ、そうした自然の森羅万象の動きの中に「カミ(神)」の生成と顕現を見てとる里山・奥山的な感知力が最終的に「カミ(神)」という統合「フォルダ=風呂敷」の中に織り込まれて畳み込まれていったわけである。
そのような自然地理学的・歴史地理学的・文化文明論的条件の中で、「日本列島の宗教的心性」は形成されてきたのである。つまるところ、プレート集合と文化集合の集結点ないしユーラシア環太平洋祭祀文化の交響が「神道」の基盤であり、日本列島に展開してきた「神道」は日本列島の自然と文化の立体交差点であったと総括できる。
こうした「風土」の中で「神道」というやおよろず(八百万)型土着型宗教と「色即是空」という「即」の論理を持つ「仏教」という伝来宗教が「習合」して「神仏習合」という日本型宗教複合の習合文化を生み出していったのである。この「神神習合~神仏習合」文化は現在に至るまで日本文化の通奏低音をなしている。
このように、「神仏習合」という文化習合が練り上げられる遥か以前から、日本列島は4つのプレート集合の地で、そこに東西南北から4つの海流が流れてきて合流するという海流の十字路でもあり、そんなプレートや海流の合流点に、いろいろな「カミ」が合流してきて、そこに交響楽的に「神神習合」の文化特性ができ、その上に、ようやくにして6世紀なって仏教が朝鮮半島から伝えられ、さらには中国大陸から本格的に伝えられて、在地の神道と交じり合う「神仏習合」ができてきたというのが小論の結論である。
「神仏習合とは神神習合の一分枝(ブランチ)である」であり、そうした「集合-習合」性に基づく「多様性」が「日本の宗教心」の発現としての「寛容」を生み出してきたのである。その「日本文明の多様性」を一つの国家・民族特性として、激動する21世紀を「くらげ」のようにふわふわと生き抜き、逞しく生存していく必要がある。それがわが神道論の帰結である。
信仰心蘇生のために その1(水谷周)
信仰心の維持と強化は、日常の雑事に紛れる中、強い希求の気持ちと明確な意識に基づくことが望ましい。この目的に役立つと思われる諸側面を無作為に記述する。広く人の心の傾きを念頭に置いて、一般論としての説明。全12本だが、毎月一本を順次掲載する予定。
1.人は誰でも希望や信念を持ち、あるいは持とうとする。それとは逆に、不安を抱え、自信喪失も少なくない。そういった様々な人の心は、万華鏡に例えられる。多様であるだけではなく、その様子は日々、一瞬一瞬毎に変化しているからだ。これはいわば、万国共通の、人類の生きているという半面である。
これらの万華鏡模様は、いずれもその人の将来を描くところから始まる。明日はどうなるのか、そして来年は?自分だけではなく、家族や友人の将来も心配の種になりうる。将来を描くとは、要するに人が自然に持つ想像力の賜物といえよう。想像力は人類古来の能力であることは、様々な洞窟壁画などでも知られている。船出を描いた隣には、両手を合わせている様子が書かれており、それは船旅の安全を祈っていると思われる。また古代の墓後からは、多数の副葬品が発掘されるのが普通であり、そもそも墓で埋葬すること自体、来世を思うところから出てきたのであろう。
こうして誰もが、想像力を持ち、だからこそ何かを信じないといられないということになる。それは本当の自信かもしれないし、またはきっちりまとまった信念かも知れない。以上のことを繰り返すが、希望、失望、自信、自信喪失、楽観、悲観などなど、枚挙に暇がない。要するに人間は、想像半分に生きるように生まれついているのである。この半分を体系化して、教義という形式をとるとなれば、それはもう宗教信仰そのものである。好きとか嫌いといった問題ではない。
近代社会は実証と実験に基礎づけられた科学に非常な信頼を置いてきた。その手法しか信じられないという事態である。また科学は実に多大な成果を上げて、その科学信奉の事態を支える根拠となった。つまりそれは虚偽や幻想ではない、という事実である。そのような事実を突きつけられた人類に逃げ場はなくなったかのようになった。それ以外の見地は、馬鹿か怠慢でしかないということになるのである。
しかしそれは人の半面しか認めないということでもある。これが信仰を説く一大根拠となる。信仰も好きか嫌いの問題ではなく、人間の全貌を正面から見るかどうかという問題なのである。そのような角度から、自分を見直してみるのはどうだろうか。新たな発見が持ち受けていること、必定である。その姿が、真実であるからだ。
大切なことはこの事情は、老若男女にかかわらず、人種や性別に関係ないということである。またそれを認識するのに特別の能力は求められない。要はその人が素直で、まっすぐな心を持っているかどうかである。そのような心を基本として、人生を歩みたいものだ。